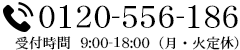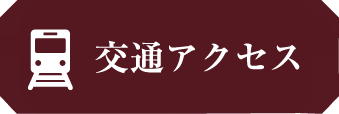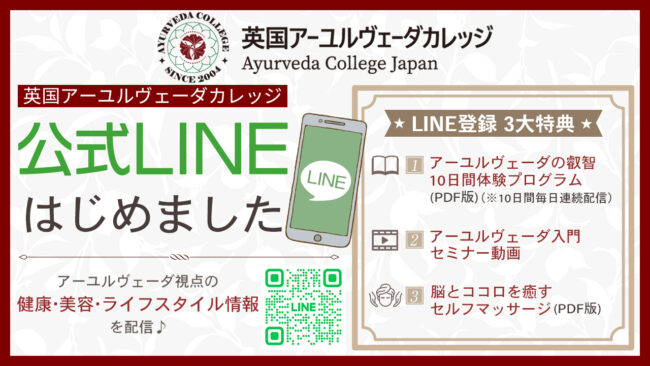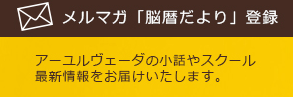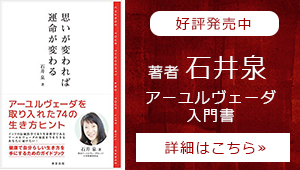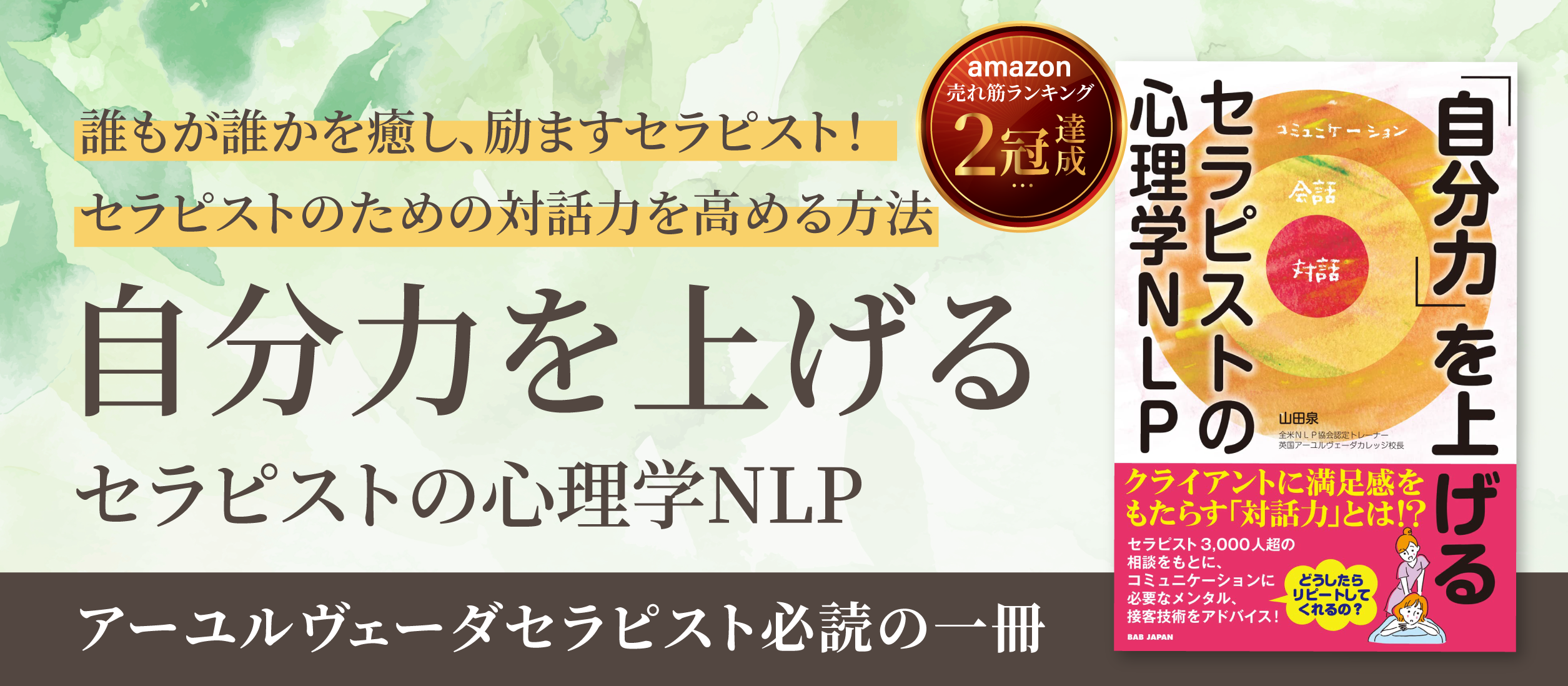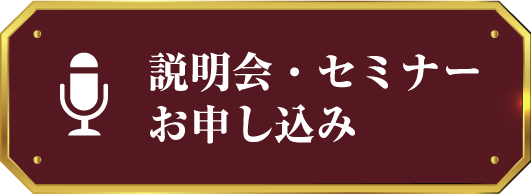梅雨になると、なんとなく体がだるかったり、気分がすっきりしなかったり…そんな不調に悩まされていませんか?
実は、アーユルヴェーダでは、梅雨は「カパ(水・地のエネルギー)」と「ヴァータ(風・空のエネルギー)」が乱れやすい季節とされており、このドーシャのアンバランスこそが、体や心の不調の原因だと考えられています。
本記事では、アーユルヴェーダの視点から、梅雨を健やかに快適に過ごすための生活習慣や食事、セルフケアの方法をわかりやすくご紹介します。薬や一時的な対処に頼らず、自然のリズムに寄り添う梅雨の養生を始めてみませんか?
目次
アーユルヴェーダで見る「梅雨」とは?
梅雨はどのドーシャが乱れる季節か?
アーユルヴェーダでは、自然界のリズムと人の体は密接に関係していると考えられており、季節ごとの変化はドーシャ(ヴァータ・ピッタ・カパ)のバランスにも影響を与えるとされます。梅雨は、雨による湿度の上昇と気温の不安定さから、「カパ」と「ヴァータ」の両方が乱れやすい季節です。
特に湿気が多く空気が重たく感じられるこの時期には、もともと「水」と「地」の要素からなるカパが増加しがちになります。一方で、梅雨の気温の変化や風、冷え込みなどによって「風」と「空」の性質をもつヴァータも刺激されやすくなります。このように、カパの重さとヴァータの軽さという相反するドーシャが、梅雨という一つの季節の中で入り乱れるため、心身に大きな負担がかかるのです。
そのため、アーユルヴェーダではこの時期を「カパとヴァータのアンバランスに注意すべき季節」と捉え、日々の生活や食事、セルフケアでバランスを整えていくことが大切とされています。

梅雨時期の特徴と体調への影響(湿気・冷え・重さ)
梅雨の特徴といえば、なんといっても「高湿度」「冷え」「空気の重たさ」です。これらの要素は、まさにカパの性質そのものであり、体内に余分な水分を溜め込ませたり、消化力(アグニ)を弱めたりする原因となります。
具体的には、体がだるく感じたり、むくみやすくなったり、食欲がわかずに消化不良を起こしたりといった不調が現れやすくなります。また、気温の変化により自律神経が乱れやすくなるため、神経が過敏になったり、気分が沈んだり、関節が痛んだりといったヴァータ由来の症状も出やすくなります。
さらに、この季節は日照時間が短くなり、太陽の熱エネルギー(ピッタ)も低下しがちなため、心と体が「湿って」「冷えて」「鈍くなる」傾向にあります。梅雨に体調を崩しやすい人が多いのは、こうした自然のリズムによってドーシャが乱れやすくなっているからです。
梅雨に乱れやすいカパとヴァータの性質と対策
カパの増加によるだるさ・無気力・体重増加
カパが増加すると、体や心に「重さ」「粘り」「鈍さ」が現れます。梅雨の高湿度によってカパが過剰になると、朝起きるのがつらくなったり、一日中ぼんやりしたり、動きたくないという無気力な状態になりがちです。
さらに、カパの特徴である「水分の保持力」が強まると、体内に余分な水分が溜まり、むくみやすくなります。このむくみや体液の停滞は、消化力の低下や体重増加の原因にもなります。
カパを整えるためには、「軽さ」「温かさ」「乾燥」を意識した生活が効果的です。たとえば、朝は早起きをして軽い運動を取り入れ、日中は消化の良い温かい食事を摂るようにしましょう。ショウガやブラックペッパー、ターメリックなど、カパを削ぐスパイスも積極的に取り入れると良いでしょう。
ヴァータの不安定さによる関節痛・神経系の乱れ
一方で、梅雨の気温差や冷えは、ヴァータを刺激しやすい環境です。ヴァータが乱れると、体の乾燥や冷えが強まり、特に関節や神経に不調が出やすくなります。朝起きた時の関節のこわばりや、なんとなく落ち着かない、眠りが浅いといった症状はヴァータの乱れによるものです。
さらにヴァータの影響はメンタルにも及び、不安感が増したり、イライラしたりといった感情の浮き沈みを引き起こすこともあります。
ヴァータを整えるためには、「温かさ」「潤い」「安定」がキーワードです。冷たい飲食を避けて、温かいスープやハーブティーを取り入れる、足湯やお風呂で体をしっかり温める、一定の時間に食事・就寝を心がけることなどが効果的です。
ドーシャ別:自分の体質タイプ別・注意点の整理
アーユルヴェーダでは、人はそれぞれ異なるドーシャの構成(プラクリティ)を持っており、体質ごとに梅雨の過ごし方も工夫が必要です。
- カパ体質の方は、湿気に非常に影響を受けやすく、体が重くなりやすい時期です。軽めの運動、スパイス多めの食事で巡りを促すことがカギです。
- ヴァータ体質の方は、気温の変化や湿度の不安定さによって関節や神経に不調が出やすくなります。規則正しい生活と保温、ゆったりとした呼吸法が有効です。
- ピッタ体質の方は比較的安定しやすいですが、湿度の高さからくる苛立ちや肌トラブルには注意が必要です。クールダウンとリラックスを心がけましょう。
アーユルヴェーダ式・梅雨を快適に過ごす生活習慣
朝のオイルマッサージ(アビヤンガ)でカパとヴァータを整える
梅雨の朝は重くて動きづらく感じることが多いですが、そんなときにおすすめなのが「アビヤンガ(オイルマッサージ)」です。特にカパとヴァータが増えやすいこの時期には、ゴマ油やトゥルシー配合のオイルを使って温かくマッサージすることで、血行を促進し、リンパの流れを整えることができます。
オイルは入浴前に使うと効果的です。関節や手足を中心に、ゆっくりと円を描くようにマッサージすることで、冷えやむくみも軽減されます。アビヤンガには、心を落ち着かせ、自律神経のバランスを整える効果もあり、梅雨時期の不調対策にぴったりです。
梅雨におすすめの運動法:ヨガと呼吸法(プラーナヤーマ)
重く沈みがちな梅雨の心と体には、軽やかさと活力を与えてくれるヨガの動きが最適です。特に、太陽礼拝(スーリヤ・ナマスカーラ)やツイストポーズ、バランス系のポーズは、カパの滞りを軽減し、代謝を上げるのに効果的です。
また、プラーナヤーマ(呼吸法)は、ヴァータの不安定さを落ち着かせるのに有効です。特に「ナーディショーダナ(片鼻呼吸)」は、心を安定させ、自律神経を整える効果が期待できます。雨で外出できない日でも、室内でできるヨガや呼吸法を日課にすることで、内側からの巡りが整い、梅雨を快適に過ごす助けとなります。
睡眠と入浴のタイミング・整え方
梅雨は、曇天続きで体内時計が乱れやすい時期です。そのため、就寝時間が遅くなったり、眠りが浅くなったりしやすくなります。こうした不調を防ぐためには、なるべく毎日決まった時間に寝起きすること、夜のブルーライトを控えることが大切です。
また、入浴はヴァータとカパの調整にとても有効です。おすすめは就寝の1~2時間前に、38~40度のぬるめのお湯で15分程度の入浴をすること。バスソルトやアロマオイルを加えることでリラックス効果が高まり、より深い眠りにつながります。
梅雨は体調も気分も不安定になりやすい季節ですが、アーユルヴェーダの生活習慣を取り入れることで、心地よく乗り越えることができます。
梅雨の食事:アーユルヴェーダで勧められる食材と避けたい食材
梅雨に積極的に摂りたい食材(ショウガ、レモン、豆類など)
梅雨は湿気が多く、消化力(アグニ)が弱まりやすい時期です。この時期に大切なのは、体内に溜まりやすい「水分」や「毒素(アーマ)」を溜めこまないように、消化に負担をかけず、アグニをサポートしてくれる食材を選ぶことです。
おすすめは、ショウガやレモン、黒胡椒、クミンなどの温性で消化を促進する食材やスパイスです。たとえば朝は、白湯にすりおろしショウガとレモンを数滴加えた「ジンジャーレモン白湯」で一日の巡りを整えるのが効果的です。
また、ムング豆や小豆などの豆類は、余分な水分を排出し、消化もしやすいためこの時期にぴったりです。旬の苦味野菜(ゴーヤ、空芯菜、春菊など)も体を軽く保つ助けになります。
消化力(アグニ)を高める調理法とスパイス(クミン、ターメリックなど)
調理法としては、「加熱」「温かい料理」「油分控えめ」「スパイスを活用」が基本です。冷たい生野菜や冷製スープは、アグニを弱めてしまうため、この時期には避けた方がよいでしょう。
特におすすめのスパイスは、クミン、フェンネル、コリアンダー、ターメリック。これらはアグニを助けつつ、体内の余分な湿気を排出してくれる働きがあります。たとえば、スパイスを効かせた消化促進スープや、ターメリック入りの温かい豆カレーなどが梅雨には適しています。
白米にクミンとギーを少量混ぜた「クミンライス」や、ターメリック味噌汁など、和食にスパイスを取り入れるのも無理なく続けやすい工夫です。
避けるべき食材(乳製品、冷たいもの、揚げ物)
梅雨に避けたいのは、「冷たいもの」「油っこいもの」「重たい乳製品」など、カパを増やしやすく、消化に時間がかかる食材です。
アイスクリームや冷たい飲料、ヨーグルトなどは、一見さっぱりしていて良さそうですが、実は体内を冷やし、湿気をため込む原因になりやすいです。特に夜間の乳製品は未消化物(アーマ)の原因となるため控えた方が無難です。
また、天ぷらや揚げ物などの油を多く含む食事も、カパを増加させてだるさや体重増加を招きやすいため、蒸す・煮るといった軽めの調理法に切り替えてみましょう。
心のバランスを保つ:梅雨時期のメンタルケア
気分の落ち込みや不安に対するアーユルヴェーダ的アプローチ
梅雨の季節は、日照時間が短くなることで気分が沈みがちになります。アーユルヴェーダでは、こうしたメンタルの変化もドーシャの乱れととらえます。特にカパが増えると、無気力や抑うつ的な感覚、やる気のなさが出やすく、ヴァータが乱れると不安感や落ち着きのなさが現れます。
このようなときは、朝日を浴びる・規則正しいリズムを保つ・食後に散歩するなど、自然とつながる生活を意識すると良いでしょう。また、ナーディショーダナ(片鼻呼吸)や深い腹式呼吸を行うことで、神経系が安定し、心も穏やかになります。
梅雨に実践したい簡単な瞑想とハーブティーの活用法
瞑想は、ドーシャのバランスだけでなく、思考をクリアにし、情緒を落ち着かせる非常に有効な手段です。特に朝や就寝前に5分間でも「今ここ」に意識を向ける時間を持つことで、梅雨の不安定なエネルギーに左右されにくくなります。
また、心の不調が気になるときにはトゥルシー(ホーリーバジル)、ラベンダー、レモンバームなどを使ったハーブティーがおすすめです。これらは精神を落ち着け、同時に体内の毒素排出も助けてくれます。
お湯にスライスショウガと蜂蜜を加えた「ジンジャーハニーティー」も、梅雨の朝に心身を温め、気分をスッキリさせる簡単なレメディです。
日本の梅雨に合ったセルフケアアイデア集
和の食材を使ったアーユルヴェーダ式レシピ例(梅干し・味噌・紫蘇など)
アーユルヴェーダの基本原則は「身近な素材で、無理なく、続けられること」。そのため、インドの伝統的なスパイスや食材がなくても、日本の梅雨に合った食材を使うことで、十分にドーシャバランスを整えることができます。
たとえば、梅干しはカパを削ぎ、ヴァータの乱れも落ち着けてくれる万能食材です。白湯に梅干しと少量の醤油を加えて「梅醤番茶」にすれば、消化を促し、体を温める一杯になります。
味噌は発酵食品ではありますが、温かい状態で摂取し、スパイスと組み合わせることで胃腸をサポートしてくれます。たとえば、ショウガやクミン、ターメリックを加えたスパイス味噌汁は、梅雨の朝食や軽食にぴったりです。
また、紫蘇や大葉、みょうが、山椒などの香味野菜は、湿気で重くなった体を軽やかにし、食欲を促進する力があります。これらを使った「薬味ごはん」や「和風スパイス炒め」は、まさにアーユルヴェーダ的な日本食といえるでしょう。
梅雨におすすめのハーブ・アロマ・市販アイテム(トゥルシー、ユーカリなど)
湿気で体も心も重たくなるこの時期、自然の香りやハーブを活用することで、五感からもドーシャバランスを整えることができます。
まずおすすめなのは、**トゥルシー(ホーリーバジル)**のハーブティー。体の内側からカパを削ぎ、呼吸器系のケアや免疫力サポートにも役立ちます。また、ユーカリやペパーミント、シトロネラなどのアロマオイルは、空気を爽やかにし、梅雨のじめじめとした環境を浄化してくれます。
市販のアイテムで手軽に取り入れるなら、アーユルヴェーダブランドのトゥルシー茶や、オーガニック精油、バスソルトなどが便利です。特に、トゥルシー+ジンジャーや、レモングラス+ミントといったブレンドティーは、心身のリフレッシュにも◎。
また、セサミオイルは全身マッサージだけでなく、耳の内側や鼻孔周りに塗るナスヤケア(鼻オイルケア)としても活用でき、ヴァータの鎮静に効果的です。
梅雨を機に心身を整える100日セルフケアのすすめ
「季節の変わり目こそ体を整えるチャンス」
アーユルヴェーダでは、季節の変わり目は「リセットと調整のタイミング」とされています。特に梅雨は、春から夏への移行期であり、体も心も揺らぎやすい時期。だからこそ、このタイミングを活かして体質改善に取り組むことで、次の季節を心地よく迎える準備が整うのです。
100日続けたい:朝の習慣/食生活/軽い運動
具体的には、朝のオイルマッサージや白湯習慣、ショウガ入りスープなどの温かい食事、ヨガやウォーキングといった軽い運動など、日々の中で無理なく続けられる習慣を「最低100日」続けてみることをおすすめします。
100日間で体は徐々に変化を感じ始めます。特にアグニ(消化力)が安定し、排出機能が整うと、むくみや疲れ、便通や肌トラブルが改善し、気分も明るくなる方が多いです。
梅雨明けに調子が良くなる体質改善プラン
この100日プランは、単なる「季節のやり過ごし」ではなく、「体質を根本から整える」ための長期的アプローチです。梅雨明けの頃には、むくみにくい体、疲れにくい心身、安定した睡眠など、さまざまな変化を感じられるでしょう。
特に、梅雨にこまめなケアを重ねておくことで、夏バテや食欲不振、熱によるイライラなど、夏特有の不調を予防することができます。
アーユルヴェーダの知恵で梅雨を心地よく乗り越えるために
梅雨はどうしても不快感が多く、体調も気分も揺らぎやすい時期ですが、アーユルヴェーダの視点を取り入れることで、自然のリズムに逆らわず、調和をもって過ごすことができます。
どんよりとした空模様に気持ちまで引きずられがちな梅雨ですが、そんな時期だからこそ、自分の心と体に優しく向き合う時間を大切にしてみませんか?
アーユルヴェーダの知恵は、「今のあなたを責めないこと」「少しずつ整えていくこと」を教えてくれます。完璧を目指す必要はありません。白湯を飲む、呼吸を整える、温かい食事を心がける——そんな小さな一歩の積み重ねが、きっとあなたの毎日を穏やかに変えてくれます。
雨音に包まれるこの季節、自分の内側を見つめ、心身をリセットする特別な時間として、ぜひアーユルヴェーダの梅雨養生を取り入れてみてください。
カパとヴァータの乱れに気づき、それに応じた食事・運動・生活習慣を選ぶことで、むくみや疲労、消化不良、不安感といった不調に振り回されることが少なくなります。何より、心地よい日々を取り戻すためのヒントが、毎日の小さな行動の中にあることを、アーユルヴェーダは教えてくれます。
雨音に包まれた日々こそ、自分自身の内側と向き合い、体と心の声に丁寧に耳を傾けるチャンスかもしれません。今年の梅雨は、自然と調和しながら、自分を整える静かな時間として過ごしてみてはいかがでしょうか。
無料個別説明会で、“あなたにとっての学びの生かし方”がわかります
英国アーユルヴェーダカレッジでは、個別での無料説明会も開催されています。
「今の私に、必要な学びなのか?」「仕事や家事と両立できる?」といった不安も、やさしく丁寧に相談にのってくれます。
また、オンライン受講や週末クラスも用意されており、無理なく続けられる柔軟な学び方が選べるのも魅力です。
本気でアーユルヴェーダを学びたい方へ
総合プロコースの詳細はこちらからどうぞ
>>総合プロコース
★プロフェッショナルなアーユルヴェーダセラピストの育成
★1年間510時間の本格的なカリキュラム
★アーユルヴェーダを深く学び、もっと健康で美しくなりたい
★セラピストとして多くの人の健康と幸福に貢献したい
★サロンを開業して、自分の自由な時間で仕事をしたい
★現状のスキルと掛け合わせてカウンセリングの質を高めたい
こんな皆さまの学びを徹底サポートします。
アーユルヴェーダの独自のオイルマッサージ法タイラヴィマルダナが学べるのは 日本国内では本校のみとなります。
入学をご検討の方は、山田泉校長の無料説明会にいらしてください。
個別無料説明会の詳細はこちらからどうぞ
>>山田泉の個別無料説明会
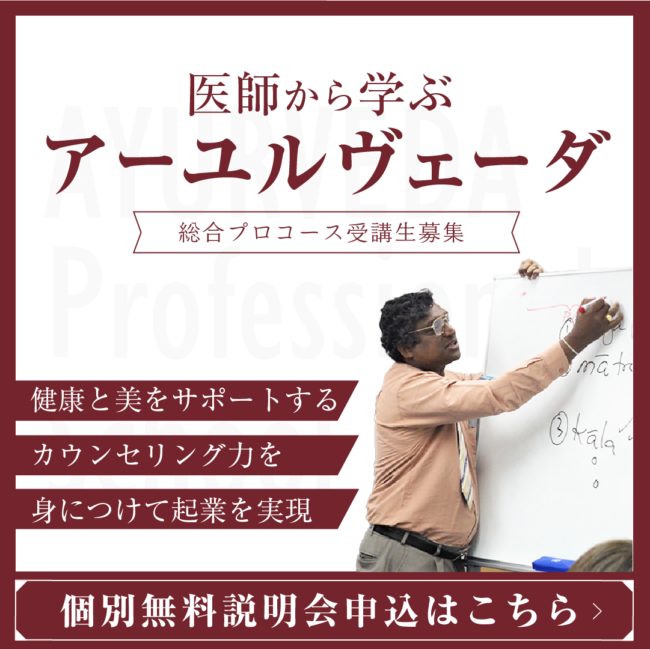
リアルな受講生の声はこちら
ライター&編集担当

東京都出身。気になることはすぐ確かめたくなる好奇心旺盛のヴァータ体質。
misaki 記事一覧へ
コロナ禍での体調管理をきっかけにアーユルヴェーダに出会う。自律神経の乱れやPMSなど、それまで悩んでいた不調にも対処できることがわかり、学びを深める。知識が増えるにつれ体調を崩すことが激減。身体が弱いと思っていたがセルフケア不足だったことに気づく。
現在は自分の体の変化を楽しみながらアーユルヴェーダを実践中。
おだやか、ていねい、マイペースな人生を送ることが目標。
英国アーユルヴェーダカレッジ56期卒業
アーユルヴェーダビューティーセラピスト/ライフカウンセラー