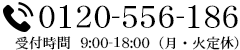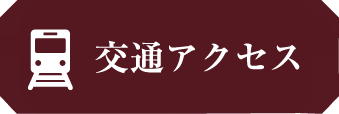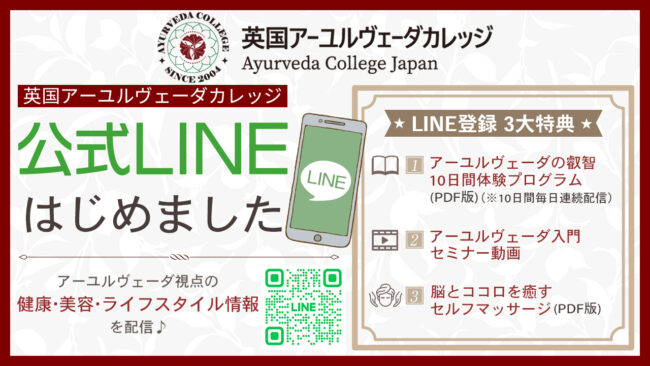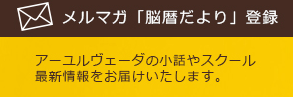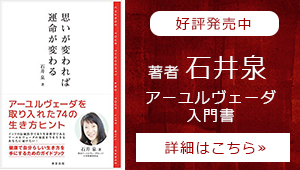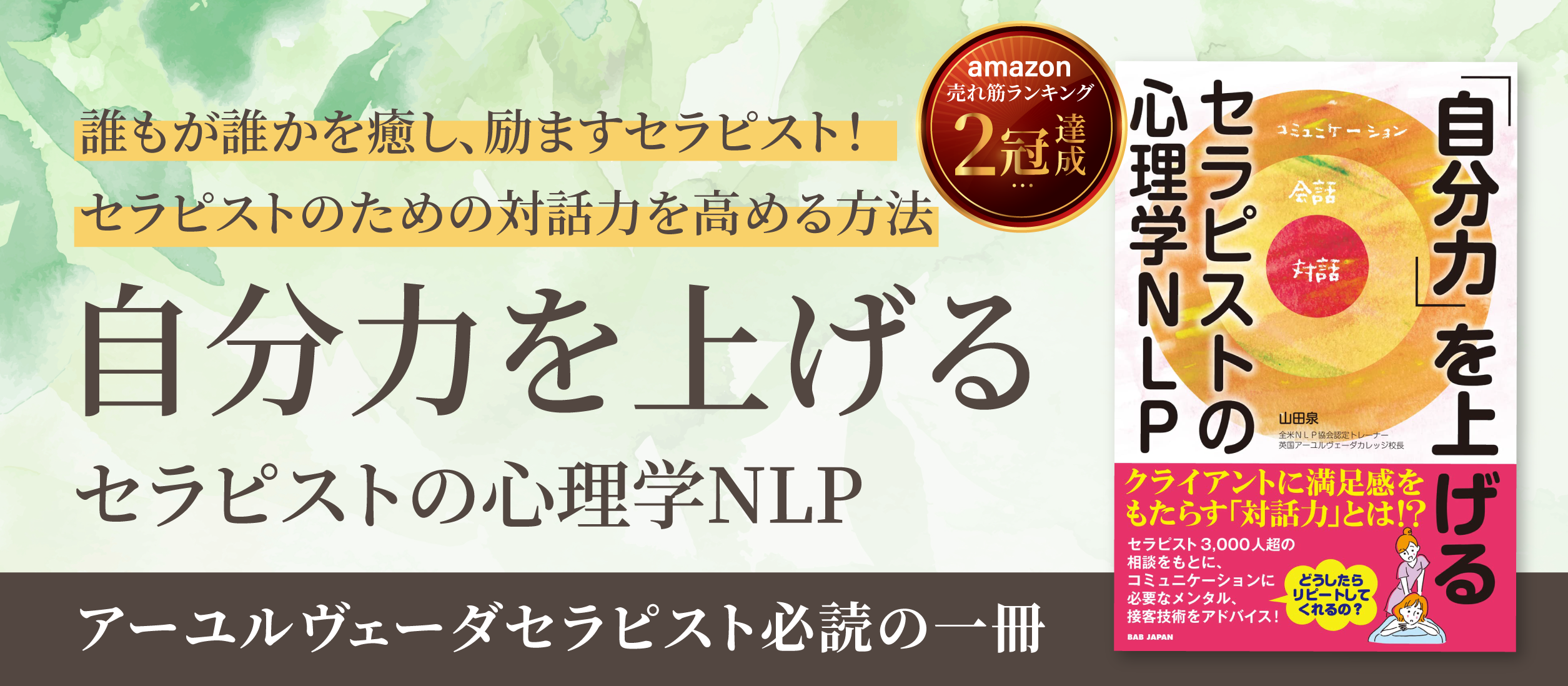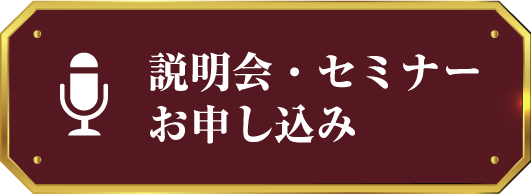アーユルヴェーダと髪の深い関係
アーユルヴェーダの考える「髪」とは?
アーユルヴェーダでは、髪は単なる外見の一部ではなく、体の健康状態を反映する指標とされています。特に注目すべきは、「髪は骨(アスティ)の副産物(マラ)である」という考えです。これは、髪が体内の骨組織と密接につながっているとする考え方で、骨の健康や代謝の状態が髪の質に大きく影響するとされています。
つまり、カルシウムやミネラルが不足していたり、骨に関わる代謝が乱れていると、髪は細くなったり、抜けやすくなったりします。これはまさに、髪が体内の状態を“映し出す鏡”であることを意味しています。
また、髪は老廃物の排出経路の一つでもあり、毛穴からは体内の熱や毒素(アーマ)も排出されます。そのため、頭皮と髪のケアは「デトックス」にもつながるとされており、美容だけでなく健康維持にも重要な役割を果たしています。
目次
髪の質は体質で決まる?ヴァータ・ピッタ・カパの髪タイプ別特徴
アーユルヴェーダでは、人の体質を「ドーシャ」と呼ばれる3つのエネルギータイプで分類します。それぞれのドーシャによって、髪の質やトラブルの傾向も異なります。
- ヴァータ(風)タイプ
髪が乾燥しやすく、細く、枝毛や切れ毛になりやすい傾向があります。量が少なく、クセが出やすいのも特徴。ストレスや不安が原因で抜け毛が増えることも。 - ピッタ(火)タイプ
毛量は中程度で、色は赤みや茶色がかった傾向に。熱がこもりやすく、白髪や抜け毛になりやすいタイプです。ピッタが過剰になると頭皮が炎症を起こしやすくなります。 - カパ(水)タイプ
髪はしっかりしていて太く、黒くてツヤがあり、量も多いタイプ。油っぽくなりやすい傾向があり、頭皮のベタつきやフケの原因になることもあります。
自分の体質を知り、それに合わせたケアを行うことが、アーユルヴェーダのヘアケアの第一歩です。
髪は“消化力のバロメーター”!? アグニ(消化の火)の重要性
アーユルヴェーダで「アグニ」と呼ばれる消化の火は、髪の健康とも密接に関わっています。アグニがしっかりと機能していると、食べ物が適切に消化・吸収され、髪に必要な栄養も骨、そして髪にスムーズに届けられます。しかし、アグニが弱っていると、未消化物(アーマ)が体内に蓄積し、これが髪の不調や頭皮トラブルの原因となるのです。
例えば、脂っこい食事や過剰な冷たい飲食物、ストレスなどはアグニを弱めます。反対に、生姜湯やスパイスを適度に取り入れる食事は、アグニを高める手助けになります。つまり、美しい髪を育むには、外からのケアだけでなく、内側=消化機能を整えることも不可欠なのです。
日々の習慣で差がつく!アーユルヴェーダ的ライフスタイルで美髪を育む

ヘアケアのルーティンを見直す:「洗う・乾かす・整える」の黄金バランス
アーユルヴェーダでは、髪の洗いすぎはドーシャバランスを崩す原因になると考えられています。理想は3日に1回程度、ぬるま湯での洗髪がすすめられています。熱すぎるお湯は頭皮を乾燥させ、ヴァータを乱すため避けるのがベター。
シャンプー後は、自然乾燥が推奨されています。ドライヤーの熱は髪を傷め、ピッタを増悪させる、もしくは強風モードであればヴァータが増悪します。ただし、それは「頭部が冷えすぎない」「湿ったまま長時間放置しない」ことが前提です。髪が濡れたままで長時間いるとカパが増えやすくなり、頭痛・鼻づまり・だるさ・眠気の原因となります。特に寒い季節・朝・体質的にカパ優勢の人には注意が必要です。低温のドライヤーで短時間で乾かすというのが、バランスのとれた対処法なのではないでしょうか。
また、ブラッシングも丁寧に行うことで、頭皮の血行促進やドーシャの調整につながります。ニームやサンダルウッドでできた広歯の木製櫛が特におすすめです。
季節・月のリズムに合わせた髪ケア
アーユルヴェーダは、自然のリズムと調和して暮らすことを大切にしています。季節の変わり目や月の満ち欠けも、髪と頭皮の状態に影響を与えるとされます。
たとえば、満月の時期は体が水分をためこみやすくなります。頭皮がベタついたり、老廃物の排出が鈍くなるためフケが出たりしやすくなります。この時期は、クレイやシカカイのパウダーでやさしく頭皮を洗浄するのがよいでしょう。
一方で、新月はデトックスのタイミング。オイルマッサージで頭皮を柔らかくし、老廃物の排出を促すケアがおすすめです。
紫外線とピッタの関係:日中の帽子の使い方と日除け対策
ピッタ体質の方は、日差しに弱く、紫外線によって頭皮の炎症や抜け毛が起こりやすい傾向があります。そのため、外出時には帽子やスカーフで頭部を保護するのが有効です。
特に真夏の昼間や、長時間の屋外活動時は、ピッタのバランスが崩れやすくなるため要注意です。帽子は通気性の良い素材で、白やベージュなど、ピッタを鎮める淡い色を選ぶとよいでしょう。
体質別に選ぶオイル&ハーブ:セルフケアで髪と心を整える
体質別オイルの使い分けガイド
オイルを使用したヘッドマッサージは、髪だけでなく心や神経にまで作用します。自分のドーシャタイプに合わせたオイルを選ぶことで、その効果はさらに高まります。
- ヴァータタイプの方には、体を温める作用のある太白ごま油が最適です。乾燥しがちで繊細なヴァータの髪質をしっとりと包み込み、リラックス効果も期待できます。
- ピッタタイプの方は、熱を持ちやすいのでココナッツオイルがおすすめ。冷却作用があり、頭皮の炎症や赤み、フケを鎮めてくれます。
- カパタイプの方には、ごま油をベースにブリンガラジオイルをブレンドするとよいでしょう。カパは重たくなりがちなので、頭皮を活性化する成分でバランスをとります。
なお、ブリンガラージ(Eclipta alba)は“髪の王”とも呼ばれ、髪の健康・成長を促す最強のハーバルオイルです。ヘッドマッサージ・ヘアケアに使用され、体質を問わず使用できる万能オイルとしても人気があります。
アーユルヴェーダハーブ図鑑:アムラ・シカカイ・ニーム・ヘナ・アロエベラ
美髪を目指すうえで欠かせないのが、ハーブの力を活用することです。以下に、代表的なアーユルヴェーダハーブをまとめました。
- アムラ(アンマロク、Phyllanthus emblica)
「若返りの果実」とも呼ばれるスーパーフードで、ビタミンCが豊富。粉末やペーストにして頭皮に塗布すると、抜け毛や白髪の予防に効果があります。 - シカカイ(Acacia concinna)
「髪の果実」とされる洗浄用ハーブ。サポニンを含み、天然のシャンプーとして使われます。髪にツヤを与え、頭皮をやさしく洗い上げます。 - ニーム(Azadirachta indica)
抗菌・抗炎症作用に優れたハーブで、頭皮トラブルやフケのある方におすすめ。ニームオイルや粉末を使ったパックは、頭皮環境の改善に役立ちます。 - ヘナ(Lawsonia inermis)
白髪染めとして知られていますが、髪を補修し、自然なコシとツヤを与えるトリートメント効果もあります。毛穴を引き締め、髪の立ち上がりをよくします。 - アロエベラ(クマーリー)
保湿効果が高く、乾燥した頭皮や髪に潤いを与えます。アムラやニームと組み合わせてパックにするのも人気です。
これらのハーブは、単体でも効果的ですが、オイルやヨーグルトなどとブレンドすることで相乗効果が期待できます。
ハーブ×オイルで作るマッサージブレンドの基本レシピ
ご自宅で簡単にできるヘアマッサージオイルのレシピをご紹介します。素材はすべて自然由来で、頭皮にも環境にもやさしいものばかりです。
■基本の育毛ブレンド(ヴァータ・ピッタ共通)
- 太白ごま油 30ml
- アムラパウダー 10g
- フェヌグリークシード(粉末) 小さじ1
- ブリンガラージオイル 数滴(市販のもの)
これらを湯煎でほんのり温めてから頭皮になじませ、指の腹で優しくマッサージします。週2回程度が理想。頭皮にしっかり浸透させたあとは、30分ほど置いてから洗髪しましょう。
■クールダウン&フケ予防ブレンド(ピッタタイプ向け)
- ココナッツオイル 30ml
- ニームパウダー 小さじ1
- ライム果汁 小さじ1(オイルに混ぜる際は直前に)
夏場や頭皮がかゆいときにぴったり。冷却作用のある素材で、ピッタを整えながら頭皮をクレンジングできます。
自宅でできる体質別ヘッドマッサージ法【イラスト付き想定】
オイルを選んだら、次は正しいマッサージ法でドーシャを整えましょう。以下は体質別のおすすめ手技です。
ヴァータタイプ:包み込むように“ゆるめる”ケア
- 両手で頭を優しく包み込み、手のひら全体でじわ〜っと圧をかける
- 額から後頭部に向かってなで下ろすように動かす
- ストレスや不安が強いときにもおすすめ
ピッタタイプ:熱を冷ます“ゆっくりとした円運動”
- 指の腹を使って、生え際から円を描くようにマッサージ
- 強くこすりすぎないよう意識して
- 頭皮が赤くなりやすい方に特に効果的です
カパタイプ:リズミカルに“目覚めさせる”刺激
- 髪を根元から軽くつかんで、やさしく引っ張る
- 指先でトントンとリズミカルに軽くたたく
- 眠気やだるさを感じる朝におすすめです
マッサージのタイミングは入浴前か夜寝る前がベスト。心地よさを感じながら、自分の体と対話する時間として取り入れてみてくださいね。
髪の内側からのケア:アーユルヴェーダ的“美髪食”と食事習慣
食べることで髪が育つ!? 消化力アグニを整える基本の食事術
アーユルヴェーダにおいて美しい髪は、外からのトリートメントだけでなく、「内側からのケア」が非常に大切だとされています。その中でも最も重視されるのが消化力=アグニです。
アグニとは、食べ物を“消化・吸収・代謝”する力のことを指し、これが弱まるとどんなに栄養価の高いものを摂っていても、髪まで届かず、未消化物=アーマとなって体に滞ってしまいます。
アグニを整えるための基本の食事習慣は、以下の3つです。
- 温かく消化に良いものを中心に:冷たい飲み物や生野菜ばかりではアグニが冷え、働きが鈍くなります。スープや温野菜、ギー(後述)を加えた炊き込みご飯などがおすすめです。
- 決まった時間に食べること:不規則な食事は体内リズムを乱し、アグニに負担をかけます。特に昼食は1日の中で最もアグニが強くなる時間帯(10時〜14時)なので、しっかり食べましょう。
- 食べ過ぎ・間食を避けること:満腹になるまで食べると、アグニが追いつかず、未消化物が髪に悪影響を及ぼします。「腹八分目」が黄金バランスです。
アグニをサポートする食品としては、生姜(しょうが)やクミン、フェンネルなどの消化促進スパイスを少量ずつ取り入れるとよいでしょう。とくに朝、白湯に薄切りの生姜を加えて飲む「ジンジャー白湯」はおすすめです。
朝昼夜の理想的な食事法と摂るべき6味(甘・酸・塩・辛・苦・渋)
アーユルヴェーダでは、「6つの味(ラサ)」=甘味、酸味、塩味、辛味、苦味、渋味のバランスを取ることが、心身の調和、そして髪の健やかさにもつながると考えられています。
■6つの味とその役割
| 味 | 体への働き | 髪への影響 |
| 甘味(米、フルーツ、ミルクなど) | 滋養を与え、潤いを保つ | 髪に栄養とツヤを与える
太く健康な髪へ導く |
| 酸味(レモン、ヨーグルト) | 食欲を促し、唾液分泌を助ける | 頭皮の血行を促進し、毛根への栄養供給を助ける |
| 塩味(天然塩、味噌) | 水分バランスを調整 | 頭皮の乾燥防止 |
| 辛味(唐辛子、生姜) | アグニを刺激し、代謝を上げる | 毛根への血流促進 |
| 苦味(ゴーヤ、葉野菜) | デトックス、毒素排出 | 皮脂の過剰分泌を抑え、脂性フケを防ぐ |
| 渋味(豆類、緑茶) | 引き締め、吸収の抑制 | 収斂作用があり、頭皮を引き締める
|
食事は「薬」と同じ。毎日のメニューに6つの味をバランスよく取り入れることで、体と髪は自然と整っていきます。
美髪の味方!ピッタ抑制に効くアムラの取り入れ方
アムラは、アーユルヴェーダで“若返りの果実”と呼ばれるスーパーフード。特にピッタ体質の人の髪トラブル(抜け毛・白髪・頭皮の炎症)に対して、非常に高い効果が期待されています。
アムラには以下のような特性があります。
- ビタミンCがレモンの約10倍(100gあたり)
- 活性酸素の除去=抗酸化作用
- 頭皮のクールダウン効果
- 免疫力と代謝のサポート
■アムラの取り入れ方3選
- アムラパウダーを水やギーと混ぜて朝に摂取
→ 小さじ1のパウダーを白湯に溶かして飲むと、体の内側からクレンジングが始まります。 - アムラを使ったヘアマスク(詳細は5章にて)
→ オイルやヨーグルトと混ぜて、髪に塗布。白髪予防や髪の強化に役立ちます。 - アムラ入りサプリメント
→ 忙しい方は、信頼できるオーガニックブランドのアムラタブレットを日常に取り入れるのも◎。
アムラはトリファラ(3種の果実)のひとつとしても知られ、腸内環境の改善にも用いられています。腸が整えば、栄養の吸収率もアップし、結果として「髪まで届く栄養」が増えるという、嬉しい循環が生まれるのです。
お悩み別!髪トラブルをケアするアーユルヴェーダ・ホームレメディ大全
抜け毛予防:フェヌグリーク&ヨーグルトの強髪パック
抜け毛の原因は、ストレス、栄養不足、頭皮の炎症や血行不良などさまざまですが、アーユルヴェーダではこれをヴァータやピッタの乱れによるものととらえます。ここで効果的なのが、**フェヌグリーク(Methi)**とヨーグルトを使ったパックです。
【材料と作り方】
- フェヌグリークシード 15g(大さじ1〜1.5杯)
- プレーンヨーグルト 大さじ2
- ハチミツ 小さじ1(保湿目的でプラス)
- フェヌグリークを一晩水に浸して柔らかくします。
- 翌日、ペースト状になるまですりつぶします。
- ヨーグルトとハチミツを混ぜて、頭皮と髪に塗布。
- 30分ほど置いてから、ぬるま湯で丁寧に洗い流します。
週2〜3回続けると、毛根が強化され、抜け毛が減少していきます。フェヌグリークは高いタンパク質とレシチンを含み、毛根の栄養補給に優れています。
枝毛対策:赤玉ねぎ×ココナッツオイルで補修パック
枝毛は、髪の乾燥や熱ダメージによってキューティクルが裂けることで発生します。ここで活躍するのが、赤玉ねぎのエキスとココナッツオイルのコンビ。赤玉ねぎには、血行を促す硫黄化合物が豊富に含まれており、髪の再生力をサポートしてくれます。
【材料と作り方】
- 赤玉ねぎ 1/4個(約25g)
- ココナッツオイル 小さじ2(約10ml)
- 玉ねぎをすりおろし、布で絞って汁だけを取り出します。
- ココナッツオイルと混ぜてペースト状にします。
- 髪全体に塗り、20分置いてからぬるま湯で洗い流します。
週1〜2回の使用がおすすめです。髪のダメージ補修だけでなく、毛先までしっとりツヤが戻ると評判のレメディです。
フケ・かゆみに:ライム×生姜×オリーブのトニック
フケや頭皮のかゆみは、ピッタの過剰や頭皮の乾燥・脂漏が原因になることがあります。アーユルヴェーダでは、頭皮の清浄とクールダウンがポイント。ここでは、消炎・抗菌作用のある素材を使った“天然トニック”をご紹介します。
【材料と作り方】
- ライム果汁 小さじ1
- 生姜汁 小さじ1
- オリーブオイル 小さじ1
- すべての材料を同量で混ぜ、軽く温めます(体温程度)。
- 指の腹を使って頭皮全体に塗布し、優しくマッサージ。
- 1時間放置した後、ハーブ系シャンプーで洗い流します。
特に夏場のべたつきや、帽子のムレによる頭皮トラブルに効果的。週1回のケアで、スッキリ爽快な頭皮に。
髪のボリュームUP:ハイビスカス&カレーリーフマスク
ボリュームが出ない、髪がぺたんこになりやすい方におすすめなのが、インドで古くから愛されるハイビスカスの花とカレーリーフを使ったマスクです。これらの植物は、毛根の活性化や新毛の育成に効果があるとされています。
【材料と作り方】
- ハイビスカスの花 5〜6輪
- ハイビスカスの葉 2枚
- カレーリーフ ひとつかみ(10〜15枚)
- アムラパウダー 小さじ1
- セサミオイル or ココナッツオイル 大さじ1
- すべての材料をミキサーで滑らかなペーストに。
- 髪全体に塗布し、シャワーキャップでカバー。
- 30分置いた後、ぬるま湯で洗い流します。
週1〜2回の使用で、髪にハリとコシが蘇り、自然なボリューム感が出てきます。
髪の乾燥・パサつきに:バナナ+蜂蜜+アーモンドオイルの保湿マスク
乾燥した髪やパサつきが気になるときは、栄養と水分を一気に与える保湿マスクが効果的です。バナナにはビタミンB群、蜂蜜は天然の保湿剤として、アーモンドオイルは髪をなめらかにする働きがあります。
【材料と作り方】
- 熟したバナナ 1/2本(約75g)
- プレーンヨーグルト 大さじ1(約15g)
- 蜂蜜 小さじ1(約15ml)
- アーモンドオイル 小さじ1
- 材料をすべてボウルでよく混ぜ、クリーム状にします。
- 髪の根元から毛先まで塗布し、20分放置。
- 洗い流した後は、自然乾燥が理想です。
乾燥しやすい冬や冷房の効いた室内に長時間いる方にぴったりのケアです。週1〜2回の継続で、髪がしっとりとまとまりやすくなります。
薄毛・白髪対策:ブリンガラジ×アムラで頭皮活性マスク
年齢とともに気になる白髪や薄毛の悩み。アーユルヴェーダではこれをピッタやヴァータのアンバランスが長期的に続いた結果と捉え、頭皮の血行と冷却、毛根の活性化がポイントになります。
【材料と作り方】
- ブリンガラージパウダー 小さじ1
- アムラパウダー 小さじ1
- 太白ごま油 大さじ1
- 材料を混ぜてペーストを作ります。必要に応じてぬるま湯で緩めてもOK。
- 頭皮中心に塗布し、円を描くようにマッサージ。
- 30分放置後、ハーブシャンプーで洗い流します。
継続することで、白髪の進行を穏やかにし、髪のコシが戻ってくると多くの方に好評です。
髪だけじゃない!ヘッドマッサージがもたらす心と体の好循環
頭・耳・足裏:アーユルヴェーダ3大マルマポイントの解説
アーユルヴェーダには、「マルマ(Marma)」と呼ばれる生命エネルギーの交差点=ツボのようなエネルギーポイントの概念があります。体内には107のマルマがあるとされており、特に頭・耳・足裏の3つは心身のバランスに大きく影響を与える重要な部位です。
- 頭部のマルマ(シロー・マルマ)
頭頂部には「アディパティ・マルマ」と呼ばれるポイントがあり、精神の安定や集中力に深く関わります。ここをマッサージすることで、脳神経の緊張を緩め、深いリラクゼーションが得られます。 - 耳のマルマ(カルナ)
耳は自律神経とつながりが深く、優しく引っ張ったり回したりすることで、内臓の調整やホルモンバランスの安定につながるとされています。 - 足裏のマルマ(パーダ)
足裏には全身の臓器につながる反射区が集中しており、特に「カンダ・マルマ」は骨髄や免疫系に作用するとされます。頭と足を同時にケアすることは、エネルギーの循環を整える最も理想的な方法です。
このように、ヘッドマッサージは単なるリラクゼーションではなく、全身のエネルギーバランスを整えるための重要な施術なのです。
ストレス軽減・睡眠改善・脳疲労ケアにも効く理由
現代社会において、ストレスによる不眠や慢性的な脳疲労を感じている方は非常に多いのではないでしょうか。そんなときにこそ、アーユルヴェーダのヘッドマッサージが力を発揮します。
■なぜヘッドマッサージが心に効くのか?
- 頭皮と脳は神経で直結しており、刺激がそのままリラックス信号として伝わります。
- オイルの香り(セサミオイル、ブリンガラージ、ラベンダーなど)は、嗅覚を通じて自律神経を落ち着かせる作用があります。
- 軽く触れる・なでるという行為は、「オキシトシン(癒しホルモン)」の分泌を促進し、心の安定や安心感をもたらします。
特に寝る前のオイルマッサージは、副交感神経を優位にし、自然な眠りへと導いてくれます。ピッタやヴァータが乱れがちな現代人にとって、この習慣は心身を整える最高のセルフケアです。
経皮吸収を意識した「食べられるレベルの素材」を選ぶ重要性
アーユルヴェーダでは、肌に塗るもの=食べても安全なものという考え方があります。とくに頭皮は、顔よりも経皮吸収率が高いとされており、使用するオイルや素材の質が非常に重要になります。
■安心・安全な素材の選び方ポイント
- 化学合成成分のない100%ナチュラルなオイルを選ぶ
→ 市販のオイルには香料や保存料が含まれていることがあるので、原材料をよく確認しましょう。 - オーガニック認証を受けたハーブパウダーを使用する
→ 特にアムラ、ブリンガラージ、ニームなどは、無農薬栽培されたものがおすすめです。 - 手作りできる場合は、できるだけ新鮮な状態で使うこと
→ 生の食材は、冷蔵保存で数日以内に使い切りましょう。
「皮膚は第2の口」とも言われています。だからこそ、“食べられるくらい安心なもの”でケアすることが、結果的に美髪への近道なのです。
よくあるQ&Aと実践のヒント
よくある質問:毎日のオイルマッサージは必要?
Q. オイルマッサージは毎日やるべきですか?
理想は毎日ですが、必ずしも毎日でなくても大丈夫です。理想は週に2〜3回できるとよいですね。
忙しい方は、週末の夜に“セルフケアデー”として取り入れるのが続けやすい方法です。
休日前の夜にこんな習慣づくりはいかがでしょうか♪
- 入浴前に「ブリンガラージオイル+アムラパウダー」で軽く頭皮をマッサージ
- 湯船に浸かってリラックス(オイルが温まって浸透)
- 洗髪後は自然乾燥もしくは短時間で低温でドライヤー使用
これだけでも、髪のしっとり感や抜け毛の減少を感じる方が多いです。
実践に役立つ!おすすめの習慣化テクニック
■ポイントは「頑張らない」「自分なりのルールを作る」
習慣にするには、“完璧主義”を捨てるのがコツです。
アーユルヴェーダは本来「楽しんで続けるための智慧」なので、あなたの生活に合う形で取り入れるのが正解。
例えば、こんなふうに取り入れてみましょう:
- スキンケアの延長で1分マッサージ:
「顔の保湿後にオイルを指に少しつけて、ついでに頭皮をくるくる」 - 料理と連動させる:
「アムラパウダーをヨーグルトに入れて朝食に。残りを頭皮パック用にとっておく」 - 曜日を固定する:
「金曜夜はハーブ洗髪の日」など、自分の生活サイクルにあわせて決めておくと楽しく続きます。
まとめ:アーユルヴェーダで髪を育てよう
美しい髪を育てるということは、単に見た目を整えることではありません。
それは、心と身体の調和を大切にし、自分自身と向き合うことでもあります。
アーユルヴェーダでは、髪は骨の副産物と考えられ、消化の力「アグニ」や、私たちのエネルギーである「ドーシャ」と密接に関係しています。つまり、髪の健康は、心・食事・生活すべてのバランスの中に宿るものなのです。
朝の白湯一杯、週末のオイルケア、気が向いた日のブラッシング――
アーユルヴェーダの考え方において、「一度で完璧に変える」よりも、「小さなことを日々積み重ねていく」ことが効果に繋がります。
今日から始められることを、あなたのペースで少しずつ。
髪が変わる頃には、あなたの暮らしや心も整っているはずです。
無料個別説明会で、“あなたにとっての学びの生かし方”がわかります
英国アーユルヴェーダカレッジでは、個別での無料説明会も開催されています。
「今の私に、必要な学びなのか?」「仕事や家事と両立できる?」といった不安も、やさしく丁寧に相談にのってくれます。
また、オンライン受講や週末クラスも用意されており、無理なく続けられる柔軟な学び方が選べるのも魅力です。
本気でアーユルヴェーダを学びたい方へ
総合プロコースの詳細はこちらからどうぞ
>>総合プロコース
★プロフェッショナルなアーユルヴェーダセラピストの育成
★1年間510時間の本格的なカリキュラム
★アーユルヴェーダを深く学び、もっと健康で美しくなりたい
★セラピストとして多くの人の健康と幸福に貢献したい
★サロンを開業して、自分の自由な時間で仕事をしたい
★現状のスキルと掛け合わせてカウンセリングの質を高めたい
こんな皆さまの学びを徹底サポートします。
アーユルヴェーダの独自のオイルマッサージ法タイラヴィマルダナが学べるのは 日本国内では本校のみとなります。
入学をご検討の方は、山田泉校長の無料説明会にいらしてください。
個別無料説明会の詳細はこちらからどうぞ
>>山田泉の個別無料説明会
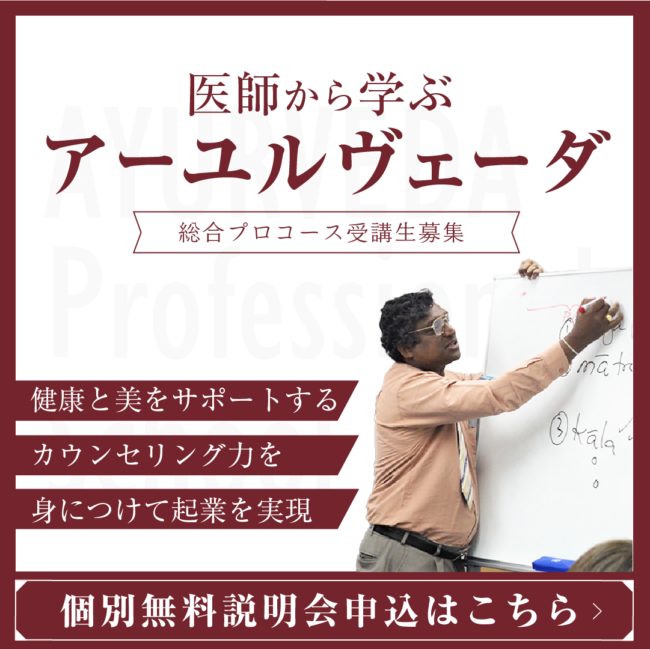
リアルな受講生の声はこちら
ライター&編集担当

東京都出身。気になることはすぐ確かめたくなる好奇心旺盛のヴァータ体質。
misaki 記事一覧へ
コロナ禍での体調管理をきっかけにアーユルヴェーダに出会う。自律神経の乱れやPMSなど、それまで悩んでいた不調にも対処できることがわかり、学びを深める。知識が増えるにつれ体調を崩すことが激減。身体が弱いと思っていたがセルフケア不足だったことに気づく。
現在は自分の体の変化を楽しみながらアーユルヴェーダを実践中。
おだやか、ていねい、マイペースな人生を送ることが目標。
英国アーユルヴェーダカレッジ56期卒業
アーユルヴェーダビューティーセラピスト/ライフカウンセラー