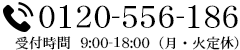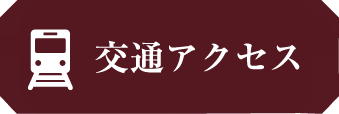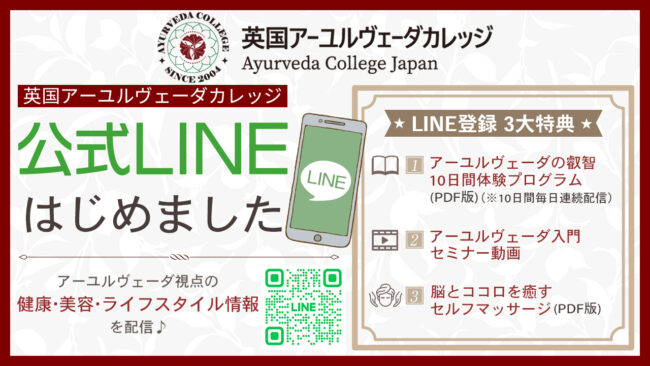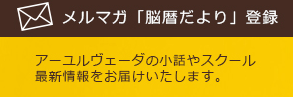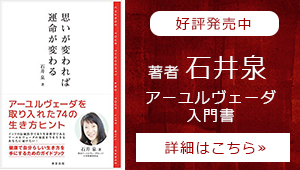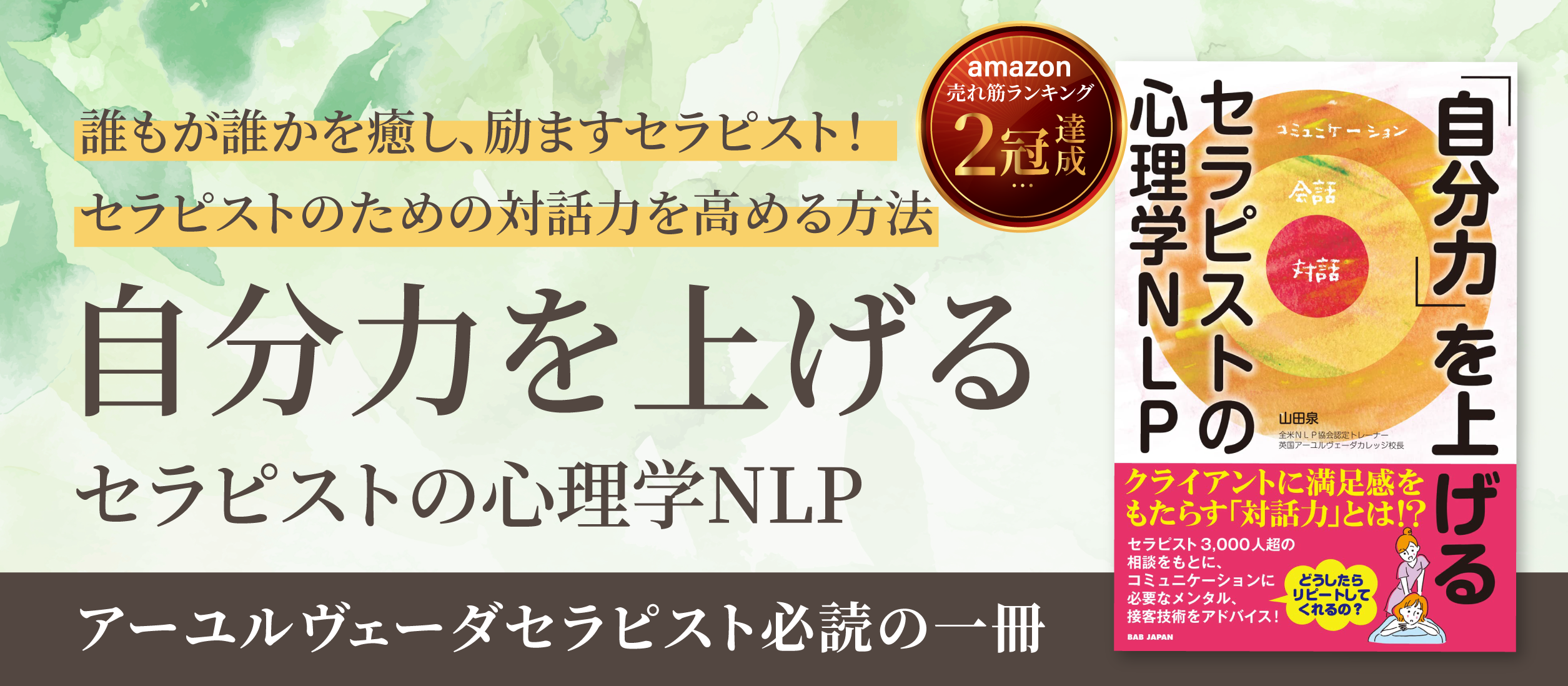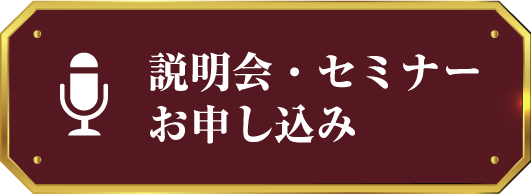毎年やってくる、厳しい夏の暑さ。
「なんだか体が重い」「食欲がない」「朝からぐったり」――そんな“夏バテ”に悩んでいませんか?
35℃超えが通常となってきている最近ですが、冷房の効いた室内と猛暑の屋外を行き来する日々。冷たい飲み物を手放せず、寝つきも悪くなって…。気がつけば心も体も疲れきっている、という方は少なくありません。
そんな現代人の夏の不調に、じんわりと寄り添ってくれるのが、アーユルヴェーダの知恵です。
古代インドで生まれた自然医学「アーユルヴェーダ」では、夏特有の体と心の乱れを整えるために、食事・生活・呼吸・ハーブといった“日常の選び方”にこそ鍵があると教えてくれます。
本記事では、アーユルヴェーダの視点から、夏バテを未然に防ぎ、もし不調になってしまった場合もやさしく回復へ導いてくれる具体的な方法を、現代のライフスタイルに合わせて詳しくご紹介していきます。
目次
- 1 アーユルヴェーダの視点から見る「夏バテ」とは?
- 2 なぜ夏は疲れやすい?科学とアーユルヴェーダの視点から
- 3 アーユルヴェーダ式・夏バテ予防の基本生活術(ディナチャリヤ)
- 4 夏に取り入れたい!アーユルヴェーダ式食事法
- 5 アーユルヴェーダ的・夏バテ回復のセルフケアと治療法
- 6 生活習慣と現代サポートのハイブリッド予防法
- 7 体質別に見る夏バテ予防・回復アプローチ
- 8 忙しい人のための「1日10分アーユルヴェーダ夏バテ対策」
- 9 まとめ:アーユルヴェーダで整える「夏を快適に生きる知恵」
- 10 無料個別説明会で、“あなたにとっての学びの生かし方”がわかります
- 11 本気でアーユルヴェーダを学びたい方へ
- 12 リアルな受講生の声はこちら
アーユルヴェーダの視点から見る「夏バテ」とは?
夏のドーシャバランスの乱れ:ピッタの増加が招く体と心の不調
アーユルヴェーダでは、私たちの体と心は「ドーシャ」と呼ばれる3つのエネルギー(ヴァータ・ピッタ・カパ)のバランスによって成り立っていると考えられています。夏は特に「ピッタ(火の性質)」が高まりやすい季節です。ピッタは消化や代謝、知性を司りますが、過剰になるとイライラ、皮膚トラブル、胃腸の不調、寝苦しさなど、体と心の両方に負担をかけます。
例えば、日中の強い日差しや高温多湿の気候は、ピッタの増加を助長します。また、熱いとついつい手を伸ばしたくなる辛いもの・酸味や塩味の強いもの・アルコールの摂取はピッタをさらに高めてしまう原因に。こうした外的・内的要因が重なることで、「夏バテ」と呼ばれる状態に陥りやすくなります。ピッタが乱れると、消化力の低下、下痢、肌荒れ、口内炎、怒りっぽさといった症状が出るのも特徴です。

アーユルヴェーダで見る「夏バテ」の具体的な症状と原因
アーユルヴェーダでは、夏バテは「ピッタの過剰」と「アグニ(消化の火)の乱れ」が原因とされます。これにより、身体の熱がこもりやすくなり、エネルギーが枯渇。実際に、日常生活で感じやすい症状としては、「食欲不振」「だるさ」「倦怠感」「下痢」「熱っぽさ」「頭痛」などがあり、感情面では「イライラ」「怒りっぽさ」「集中力の低下」が見られます。
また、汗をかきすぎてミネラルが失われたり、冷たい飲食物によって消化力がさらに低下することで、未消化物(アーマ)が蓄積し、体が重だるく感じやすくなります。こうした状態をそのままにすると、慢性的な疲労や胃腸のトラブル、免疫力の低下にもつながります。
現代医学とアーユルヴェーダの共通点:夏バテ=熱と消化のトラブル
現代医学においても、夏バテは「体温調整機能の乱れ」や「自律神経のバランスの崩れ」が主な原因とされています。特に高温多湿な日本の夏は、体がうまく熱を逃がせず、体内に熱がこもりやすい状態に。また、冷房のきいた室内と屋外の温度差が大きいため、自律神経が乱れて疲労感が増し、消化機能の低下や睡眠の質の悪化も引き起こします。
アーユルヴェーダでも、ピッタの乱れによる消化力の低下と体内の熱のこもりが「夏バテ」の根本原因とされており、現代医学と重なる点が多く見られます。こうした共通認識から、体の内外の熱バランスを調整し、消化力を高めることが、夏を元気に過ごす鍵となるのです。
なぜ夏は疲れやすい?科学とアーユルヴェーダの視点から
体温調節と自律神経の乱れ:気温・湿度が与える影響
夏になると、私たちの身体は常に高温と湿度にさらされます。この環境に適応しようとする中で、体は多くのエネルギーを使って体温を調整します。汗をかいて体温を下げようとする反面、水分とともにミネラルが流出し、脱水気味になりがちです。こうした状態は自律神経に大きな負担をかけ、疲れやすさや不調につながります。
アーユルヴェーダでも、ピッタの過剰な活性により「熱」がこもることで、神経系やホルモンバランスにも影響を与えるとされており、体内の冷却と鎮静が夏には不可欠です。
消化力(アグニ)の低下とエネルギー不足
夏は、消化の火「アグニ」が弱まる時期でもあります。気温の上昇とともに、体は自然とエネルギーをセーブするモードに入るため、消化器官の働きも鈍くなります。さらに冷たい食べ物や飲み物、アイスクリームなどを摂取すると、アグニが急激に冷やされ、食欲不振や消化不良を引き起こします。
エネルギーの元となる栄養素が十分に吸収されないと、当然ながら体はだるくなり、疲れが取れにくくなります。アーユルヴェーダでは「未消化物(アーマ)」が蓄積しやすくなり、これがさらなる疲労や不調の原因になると考えます。
睡眠・食事・冷房によるリズムの崩壊
日本の夏は、夜になっても気温が高く、寝苦しさが続きます。その結果、睡眠の質が下がり、疲労が回復しづらくなります。また、暑さのせいで食事の時間が不規則になったり、栄養バランスが偏ることも少なくありません。さらに、エアコンの効いた室内に長時間いると、体が冷えすぎて代謝が落ち、免疫力も下がります。
アーユルヴェーダでは「日々の生活のリズム(ディナチャリヤ)」が健康の鍵とされており、夏にこそ規則正しい生活を意識することが重要です。体内リズムを整えることで、自律神経も安定し、疲れにくくなります。
アーユルヴェーダ式・夏バテ予防の基本生活術(ディナチャリヤ)
朝の過ごし方:舌磨き、お水、アビヤンガ(オイルマッサージ)

朝起きたらまずは口内の洗浄をしましょう。舌磨きやうがいを行うことで、口内に溜まったアーマ(未消化物)を取り除きます。そして最初に口にするものは常温のお水、コップ1杯から2杯程度飲みましょう。夜の間に溜まった毒素を流し出し、消化の火「アグニ」を優しく目覚めさせる効果があります。
さらに、アーユルヴェーダでは「アビヤンガ」と呼ばれるオイルマッサージもおすすめです。セサミオイルでの全身マッサージもいいですが、この時期は冷性のココナッツオイルを使うのもいいですね。血流が促進され、肌の乾燥や老化防止にもつながり、心も落ち着く朝の習慣として取り入れる方が増えています。
日中の注意点:外出・運動・冷たい飲食物との付き合い方
日中は太陽のエネルギーが最も強く、ピッタも最大に高まる時間帯です。この時間に激しい運動や長時間の外出を避けることが、ピッタの過剰を防ぐ鍵となります。特に正午前後の直射日光は避け、涼しい場所での休息を意識しましょう。外出をする場合には日傘をさし、身体の負担を和らげるようにしましょう。
冷たい飲み物やアイスクリームなどの摂取は一時的には涼しく感じられますが、内臓を冷やしすぎて消化不良を引き起こすこともあるため、常温や少し温かい飲み物が理想です。コリアンダーウォーターやミントティーなど、ピッタを鎮めるハーブティーもおすすめです。
夜の過ごし方:セルフケアと深い睡眠のための工夫
夜は一日の疲れを癒やし、体をリセットする大切な時間です。22時までに寝ることが、自然のリズムに沿った理想的な生活スタイル。
スマホやパソコンなどの強い光は脳を刺激し、睡眠の質を下げるため、寝る1時間前からは使用を控えたいところです。香りを使ったリラクゼーションとして、サンダルウッドやローズのアロマオイルもピッタの鎮静に効果的です。こうした小さな工夫の積み重ねが、夏の疲れをためこまない体づくりにつながっていきます。
夏に取り入れたい!アーユルヴェーダ式食事法
ピッタを鎮める食材・ハーブ:アロエ・ミント・コリアンダー・甘味野菜

夏はピッタの増加を抑える食事がカギとなります。アーユルヴェーダでは「冷却性」があり、「甘味・苦味・渋味」の性質を持つ食材がピッタのバランスを整えるとされています。
たとえば、ミントやコリアンダーは代表的なピッタ鎮静ハーブで、ハーブティーにすることで内側から体をクールダウンしてくれます。グラスやポットの中にミントとコリアンダーシードを入れて水を注ぎ、それを冷蔵庫でしばらく冷やしておくと、熱さを和らげるドリンクのできあがり。
また、アロエベラは消化器官を整えつつ、炎症を抑える作用もあるため、夏の内臓疲れにぴったり。
野菜でいえば、きゅうり・ゴーヤ・ズッキーニ・レタス・セロリなど、水分を多く含むものが体の熱を穏やかに鎮めてくれます。果物では、スイカ・梨・パイナップル・ザクロなどもおすすめです。
避けるべき食事:辛味・酸味・塩味・揚げ物・アルコール
一方で、ピッタをさらに高める「辛味」「酸味」「塩味」の強い食事や、脂っこい揚げ物は控えめにすることが望まれます。特に唐辛子やにんにく、コーヒー、揚げ物、またアルコールや発酵食品は、ピッタを急激に上昇させる要因となります。
また、冷たいアイスやジュースの摂りすぎも消化力を冷やしてアグニの火を弱めてしまうため、「冷たいものは常温に戻してから」または「白湯と交互に飲む」など、食べ方の工夫が大切です。
消化力を落とさない食べ方:温かいもの・腹八分目・決まった時間
アーユルヴェーダでは、何を食べるかだけでなく「どう食べるか」も非常に重視されます。
食事は一日3回、決まった時間にとるのが基本で、なるべく温かいものをゆっくり噛んで食べることで、アグニ(消化の火)が安定します。早食い・ながら食いはアグニを乱し、アーマ(未消化物)を作り出してしまう原因に。
特に夏は、腹八分目を守り、消化に負担をかけないよう意識することが大切です。お腹いっぱいになると、内臓が疲れて余計に夏バテを引き起こしてしまいます。
夏におすすめのレシピ:キチュリ・ココナッツチャツネ・ライムウォーター

インドの家庭で親しまれている「キチュリ(豆粥)」は、消化に優しく栄養バランスも良いため、夏の弱った胃腸にぴったりの一品です。そこに、冷却性のある「ココナッツチャツネ」や「ミントチャツネ」を添えると、味もさっぱりしてピッタ鎮静にも効果的。
飲み物では、レモンやライムを搾った「ライムウォーター」や「ローズウォーター」も、体内の熱を静めて気分をリフレッシュしてくれます。
アーユルヴェーダ的・夏バテ回復のセルフケアと治療法
回復のためのオイル療法:アビヤンガ・シロダーラ・ナスヤ
夏バテが進行してしまった場合、アーユルヴェーダでは外側からのアプローチも非常に有効です。とくにアビヤンガ(全身のオイルマッサージ)は、体に溜まった疲労物質の排出を促し、ピッタの高ぶりを鎮める作用があります。冷房のかかっている部屋は、思っている以上に身体に疲労をもたらします。温かいセサミオイルを使うことで乾燥を取り除き、身体を滋養していきましょう。
また、シロダーラ(額にオイルを垂らすトリートメント)は、ストレスや不眠、不安感に悩む方に特におすすめ。脳のリラクゼーションと自律神経の安定に働きかけ、夏に乱れやすい心のバランスを整えます。
鼻の粘膜からオイルを注ぐナスヤは、熱による目や鼻、喉の乾燥やトラブルにアプローチします。特にアヌタイラと呼ばれる専用の薬用オイルは、頭部の熱を鎮める効果があります。
消化力を再起動する「トリカトゥ」や生姜の活用
食欲不振や胃もたれが続くときは、アーユルヴェーダで古くから使われている「トリカトゥ(生姜・黒胡椒・長胡椒のブレンド)」が役立ちます。これらのスパイスは弱ったアグニ(消化力)を刺激し、胃腸の働きを整えてくれます。ただし、ピッタを増やす性質のため、過剰摂取は禁物。食後や消化不良時のみスポット的に使い、日常的には避けるとよいでしょう。
また、生姜は消化力を上げるのにとても効果的です。「おろし生姜を加えた白湯」を朝一番に飲むことで、内側からゆるやかに代謝が上がり、体がシャキッと目覚めるのを助けてくれます。疲労が溜まっているときほど、強すぎる刺激を避けて「じんわり整える」ケアが効果的です。さらに、スライスした生の生姜にレモン汁+岩塩少々を食前30分に食べると、消化液の分泌を高め、軽いアーマ(未消化物)を減らしやすくなります。生姜と酸味はピッタをやや上げるため、暑さやイライラが強い時期は量を控えるとよいでしょう。
ピッタ鎮静に役立つハーブ療法:シャタバリ・ブラフミー・アーマラキー
アーユルヴェーダでは、体質や季節に合わせたハーブ療法も行われます。夏に増悪しやすいピッタを鎮めるには、以下のハーブがよく用いられます:
- シャタバリ:体を冷却し、女性ホルモンのバランスを整える作用があり、のぼせやイライラの改善に
- ブラフミー:神経を穏やかに鎮め、集中力や記憶力の向上に役立つとされ、夏の脳疲労にもぴったり
- アーマラキー(アムラ):ビタミンCが豊富で、抗酸化力が高く、免疫力を高めながらピッタを抑えてくれる果実
これらはハーブティーやサプリメントとして日本でも入手可能なものが増えてきていますので、体調に合わせて無理のない範囲で取り入れてみるのも良いでしょう。
呼吸と心を整える:シータリー呼吸法・月の呼吸法
身体だけでなく、呼吸を通して心を整えるのもアーユルヴェーダの基本です。特におすすめなのがシータリー呼吸法。これは、身体を冷ます呼吸法であり、冷たい空気を取り入れ、温かい空気を排出する効果があります。舌を丸めて口の外に出し、舌を通してスーッと息を吸います。冷たい空気を体内に取り込めたら舌を戻して口を閉じ、鼻からゆっくり息を吐き出します。自律神経のバランスを整え、過剰なピッタを鎮めます。
さらに、チャンドラベーダナ(左鼻呼吸・月の呼吸法)は、体を冷却しリラックス状態へ導く効果があります。左鼻で吸う→右鼻で吐くを繰り返していきます。就寝前やイライラが強いときに行うと効果的です。
どれも特別な道具がいらず、どこでもできるので、習慣として取り入れやすいセルフケアです。
生活習慣と現代サポートのハイブリッド予防法
睡眠の質を守るためのアーユルヴェーダと現代習慣
夏は気温や湿度の影響で睡眠の質が落ちやすくなります。アーユルヴェーダでは「深い睡眠(スヴァップナ)」は心と体を修復する重要な時間とされており、寝る前の過ごし方が非常に重視されます。
まずおすすめなのは、夜のオイルマッサージやぬるめの足湯で体をリラックス状態に導くこと。そこに現代的な工夫として、ブルーライトカット眼鏡の使用や、寝室を25〜27℃に保つエアコン管理を併用することで、より快適な睡眠環境が整います。
アーユルヴェーダと現代の知見を組み合わせることで、眠りの質を上げ、回復力の高い体へと導くことができます。
栄養ドリンク・漢方・サプリの正しい活用法と注意点
夏の疲労対策として、日本では「栄養ドリンク」や「漢方」「サプリメント」を活用する人も多いと思います。これらはアーユルヴェーダ的にいうと「即効性のある補助療法」にあたり、適切に使えば疲労回復のサポートになります。
例えば、タウリンやビタミンB群を含む市販ドリンクは、短時間の疲労感の軽減には効果的ですが、継続的に頼りすぎると根本的な体調改善にはつながりにくい点に注意が必要です。
一方、漢方薬では「補中益気湯」や「清暑益気湯」などが夏バテ対策として処方されることがあります。これらも医師や薬剤師に相談しながら、自分の体質に合ったものを選ぶのが安心です。
スマホ・PC使用による熱性悪化(ピッタ増大)とクールダウン対策
実はアーユルヴェーダでは、スマホやPCの過度な使用も「ピッタを高める」原因になるとされています。目はピッタに関係の深い場所のため、寝る前に使いすぎるとその分ピッタを上げてしまいます。また、ブルーライトや情報過多によって脳が興奮し、自律神経やホルモンバランスに負担がかかります。
とくに寝る前1時間はスマホやPCを見ない「デジタルデトックス」を取り入れることで、自然な眠気を取り戻しやすくなります。代わりに、アロマキャンドルやハーブティーを取り入れた夜のリラックス時間に切り替えることがおすすめです。
日焼けと肌の炎症へのアプローチ:アーユルヴェーダスキンケア法
強い紫外線を浴びると、肌のバリア機能が低下し、ピッタの熱が肌にこもって炎症を引き起こしやすくなります。アーユルヴェーダでは、ローズウォーター・アロエベラジェル・サンダルウッドペーストなどを使って肌を鎮静させる方法が古くから行われています。
特に、ローズウォーターを冷蔵庫で冷やし、コットンに染み込ませてパックする方法は、日焼け後の肌のほてりをやさしく冷まし、炎症を抑えるのに役立ちます。保湿と同時に香りでもリラックス効果が得られ、心身ともにクールダウンできます。
体質別に見る夏バテ予防・回復アプローチ
アーユルヴェーダでは、すべての人に同じ対処法が適しているとは考えません。それぞれの体質(ドーシャ)によって、夏バテの症状やその対処法も異なります。自分の体質を理解し、適切なケアを行うことが、夏を快適に過ごす第一歩です。
ピッタ体質の人:炎症・怒り・下痢への対処
ピッタ体質の人はもともと熱性が強く、夏の暑さやストレスによってピッタが過剰になると、肌荒れ・吹き出物・下痢・イライラ・口内炎などの症状が現れやすくなります。
この体質の方は、冷性のある食材(ミント・コリアンダー・きゅうりなど)を積極的に取り入れ、アルコール・辛いもの・油っこいものを控えることが重要です。精神的にも過熱しやすいため、自然の中での散歩や月光浴、呼吸法や瞑想で心を落ち着けることが大切です。
ヴァータ体質の人:疲労・冷え・不安への対処
ヴァータ体質の人は乾燥や冷えに弱く、エネルギーの消耗が激しいため、夏でも冷房による冷えや乾燥、水分不足でバテやすくなります。特に、倦怠感・不安感・便秘・食欲低下などが起こりやすくなります。
この体質の方は、温かく消化に優しい食事(おかゆやキチュリ)と、体を冷やしすぎない服装・室温管理が重要。加えて、ごま油のオイルマッサージや、足湯・ハーブティー(温性のジンジャーやシナモン)で内側から温めるケアを取り入れると良いでしょう。
カパ体質の人:だるさ・無気力・消化不良への対処
カパ体質の人は安定感があり夏バテには比較的強い傾向にありますが、湿気が多い日本の夏では体の重だるさ・無気力・胃もたれなどを感じやすくなります。特に動かないでいるとさらにエネルギーが停滞しやすいので注意が必要です。
この体質の方は、軽めの食事(蒸し野菜・スープ)やスパイス(ターメリック・ブラックペッパー)を取り入れ、適度な運動(朝のウォーキングなど)で代謝を促すことがポイントです。夏でもダラダラせず、活動的に過ごすことでエネルギーが循環し、だるさも軽減します。
体質チェックと自分に合ったセルフケアの選び方
自分の体質(ドーシャ)がわからない場合は、簡単なチェックリストや専門家のアドバイスを受けてみるのも良いでしょう。最近では、ドーシャ診断を取り入れたスパやアーユルヴェーダ施設も増えており、体質に合ったアドバイスを受けることができます。
体質を知ることで、「何を食べたらよいか」「どう休めばいいか」「どんな運動が合っているか」が見えてくるため、夏バテの予防・改善がぐっと効率的になります。
忙しい人のための「1日10分アーユルヴェーダ夏バテ対策」
毎日忙しくて、じっくりセルフケアの時間が取れない…という方にも取り入れてほしい、短時間でできる夏バテ対策をご紹介します。
朝のオイルケアと白湯で内臓を目覚めさせる
起床後、白湯を一杯ゆっくり飲み、軽くセサミオイルで顔や耳、足の裏をマッサージすることで、一日の体温調整が整い、内臓がやさしく目覚めます。忙しく5分でできるルーティンです。
食後の呼吸法とミントティーでクールダウン
ランチ後、仕事に戻る前にナーディショーダナ(片鼻呼吸)を3分間だけ行うと、頭がスッキリし集中力が回復します。さらに、ミントティーやローズヒップティーなど、ピッタを鎮めるハーブティーを一緒に飲めば、体も心もリフレッシュします。
寝る前の足湯とヘッドマッサージで深い眠りへ
お風呂が面倒な日も、足湯だけでも5分行うと、足元から血流が良くなり、心地よい眠気が訪れます。その後、ココナッツオイルで頭皮を軽くマッサージすれば、熱がこもりやすい頭部を冷やしつつ、神経の高ぶりも鎮まります。翌朝の目覚めが全く違ってくるでしょう。
まとめ:アーユルヴェーダで整える「夏を快適に生きる知恵」
夏は、心も体も乱れやすい季節です。強い日差し、蒸し暑さ、冷房と外気の気温差、睡眠不足、消化力の低下…。こうした負担が重なれば、たとえ体調を崩していなくても「なんとなく疲れている」「やる気が出ない」と感じるのは自然なことです。
そんなときこそ、アーユルヴェーダの知恵が役に立ちます。
アーユルヴェーダは、自然と調和して生きることを大切にする医学。夏のエネルギーを理解し、体と心のバランスを保つことで、不調を未然に防ぎ、今ある不快感も無理なく和らげてくれます。
例えば、朝は白湯で体内を目覚めさせ、消化にやさしい食事でピッタを抑え、夜はオイルケアや呼吸法で静かにリセットする。こうした小さな習慣の積み重ねが、夏の快適さを大きく変えるのです。
また、自分のドーシャ(体質)を知ることで、より的確なセルフケアが可能になります。ピッタ、ヴァータ、カパ、それぞれの特徴を理解し、「自分に合った方法」を選ぶことは、アーユルヴェーダの基本的な考え方です。
豪華なセルフケアや、高価なサプリに頼らなくても大丈夫。大切なのは、自分の体と丁寧に向き合い、小さな変化を積み重ねること。アーユルヴェーダの実践は、必ずしも特別な道具や環境を必要としません。忙しい方でも、1日10分の意識的な時間を持つだけで、心身の整い方が変わってきます。
「今の季節に、今の自分に必要なことは何か?」を感じ取りながら過ごすこと。それがアーユルヴェーダの夏バテ対策の本質です。季節に逆らうのではなく、季節のリズムと歩調を合わせることが、最も自然で無理のない健康法なのです。
自然と調和した暮らしが、あなたの内側から元気と穏やかさを取り戻してくれるはずです。
無料個別説明会で、“あなたにとっての学びの生かし方”がわかります
英国アーユルヴェーダカレッジでは、個別での無料説明会も開催されています。
「今の私に、必要な学びなのか?」「仕事や家事と両立できる?」といった不安も、やさしく丁寧に相談にのってくれます。
また、オンライン受講や週末クラスも用意されており、無理なく続けられる柔軟な学び方が選べるのも魅力です。
本気でアーユルヴェーダを学びたい方へ
総合プロコースの詳細はこちらからどうぞ
>>総合プロコース
★プロフェッショナルなアーユルヴェーダセラピストの育成
★1年間510時間の本格的なカリキュラム
★アーユルヴェーダを深く学び、もっと健康で美しくなりたい
★セラピストとして多くの人の健康と幸福に貢献したい
★サロンを開業して、自分の自由な時間で仕事をしたい
★現状のスキルと掛け合わせてカウンセリングの質を高めたい
こんな皆さまの学びを徹底サポートします。
アーユルヴェーダの独自のオイルマッサージ法タイラヴィマルダナが学べるのは 日本国内では本校のみとなります。
入学をご検討の方は、山田泉校長の無料説明会にいらしてください。
個別無料説明会の詳細はこちらからどうぞ
>>山田泉の個別無料説明会
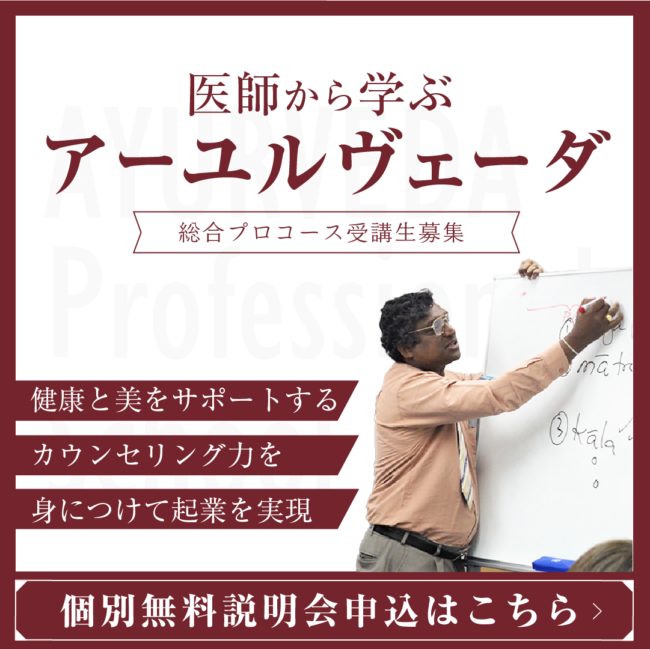
リアルな受講生の声はこちら
ライター&編集担当

東京都出身。気になることはすぐ確かめたくなる好奇心旺盛のヴァータ体質。
misaki 記事一覧へ
コロナ禍での体調管理をきっかけにアーユルヴェーダに出会う。自律神経の乱れやPMSなど、それまで悩んでいた不調にも対処できることがわかり、学びを深める。知識が増えるにつれ体調を崩すことが激減。身体が弱いと思っていたがセルフケア不足だったことに気づく。
現在は自分の体の変化を楽しみながらアーユルヴェーダを実践中。
おだやか、ていねい、マイペースな人生を送ることが目標。
英国アーユルヴェーダカレッジ56期卒業
アーユルヴェーダビューティーセラピスト/ライフカウンセラー