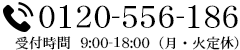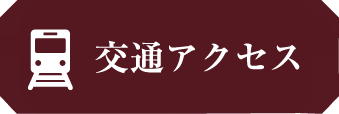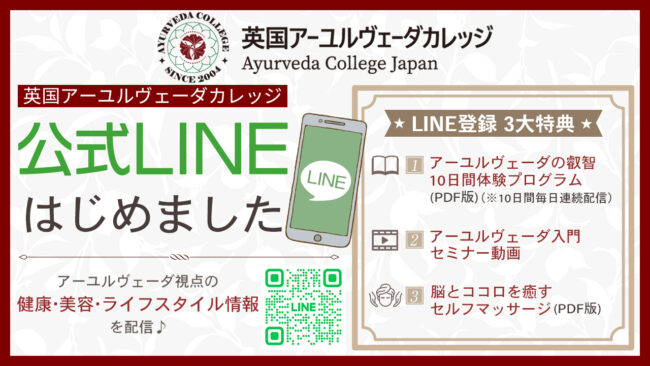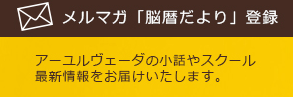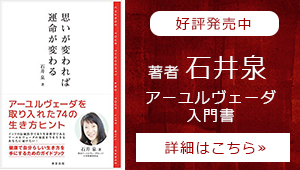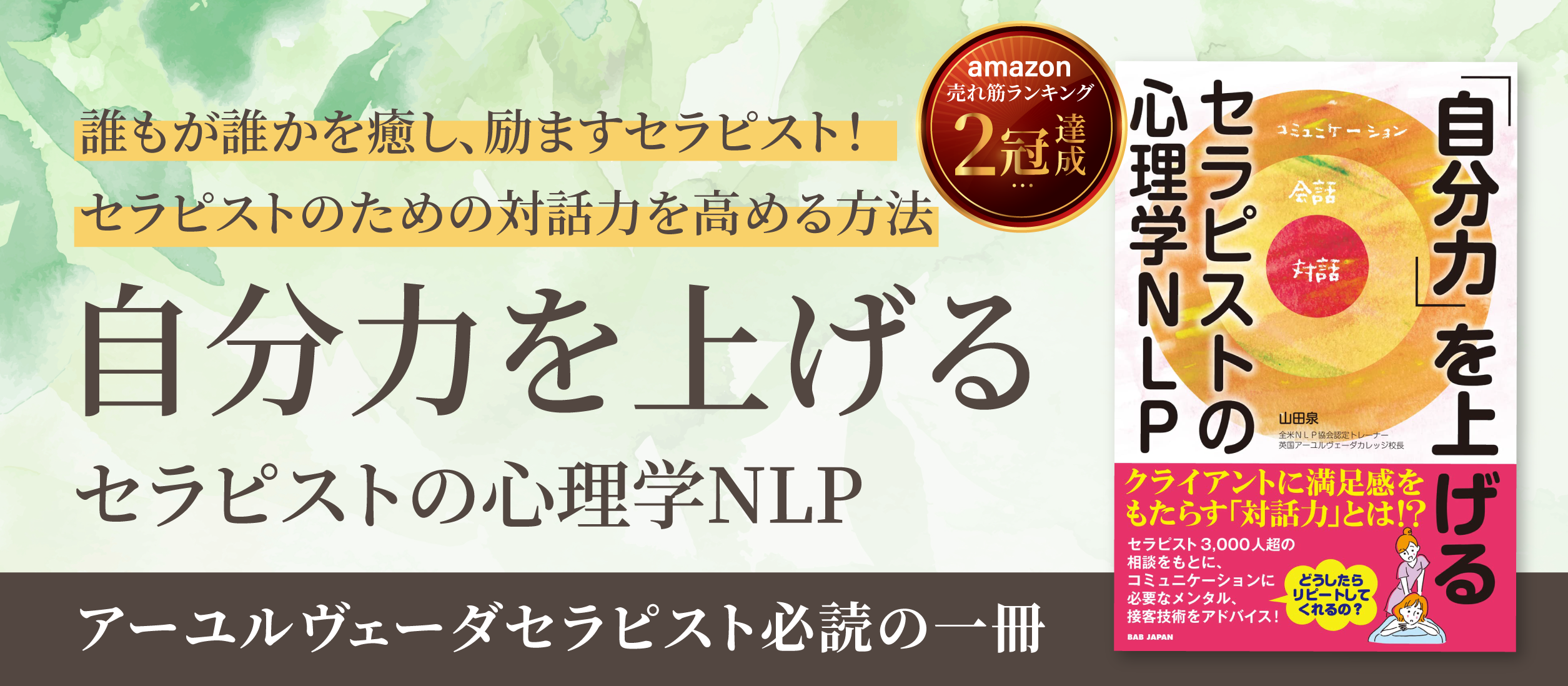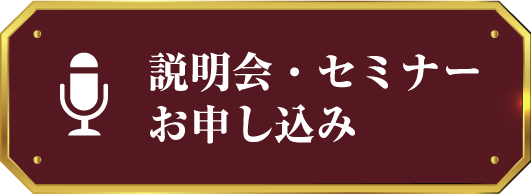じっとしていても汗ばむような日本の夏。食欲がなくなったり、なんとなくイライラしたり、胃腸の調子が不安定になったり……そんな経験、ありませんか?
実はそれ、夏特有の“体と心の熱”によるバランスの乱れかもしれません。
アーユルヴェーダでは、夏は「ピッタ(火のエネルギー)」が増える季節とされており、体の内側でも“熱”がたまりやすくなると考えられています。
だからこそ、何を食べるか、どう調理するかがとても大切。季節に合った食材と調理法で、余分な熱を穏やかに鎮めることができれば、夏の不調はぐっと楽になるのです。
今回は、アーユルヴェーダの知恵に基づきながら、日本の夏にぴったりの野菜とその取り入れ方をご紹介します。特別なことは必要ありません。ちょっとした工夫で、毎日の食事が、あなたを健やかに整える“夏の味方”になります。
目次
アーユルヴェーダで見る「夏」とは?
アーユルヴェーダでは、自然界の変化と人間の体・心は深くつながっていると考えられています。四季それぞれに対応するドーシャ(エネルギー)の変化があり、夏は火のエネルギーである「ピッタ」が自然界でも体内でも高まりやすい季節とされています。
ピッタは消化や代謝、体温調節、知性や判断力などを担う重要な役割を持っています。夏は日差しが強く、気温が高く、湿度も上がるため、体内のピッタが過剰になりやすく、心身に不調をもたらす原因になります。
そのため、アーユルヴェーダでは夏を快適に過ごすための重要なポイントとして、「ピッタを鎮める食事・生活習慣」を実践することがすすめられます。特に食事では、体の熱を和らげ、消化に優しく、心を穏やかに保つ食材選びが求められます。

夏に増えるピッタの特徴と体への影響
ピッタ・ドーシャは、火の性質を中心とした「熱」「鋭さ」「軽さ」「やや油性」「流動性」といった特徴を持ちます。夏にはこれらの性質が外界でも強くなるため、私たちの体内でもピッタが活性化されやすくなります。
具体的には、体温の上昇、汗の分泌増加、胃酸の過剰分泌、皮膚の敏感化といった身体的変化が現れやすくなります。また、精神面では、集中力や判断力が高まる一方で、怒りっぽくなったり、焦燥感を感じやすくなったりといった情緒の不安定さが目立つようになります。
こうした変化は、日常生活でのストレスや睡眠不足、不規則な食生活によってさらに増幅されることが多く、放置すると夏バテや胃腸トラブル、皮膚疾患などの体調不良を引き起こす原因になります。
ピッタの乱れが引き起こす症状(ほてり・怒り・消化不良など)
ピッタのバランスが崩れたときに最も顕著に表れるのが、「熱」の過剰による症状です。たとえば、顔や身体がほてったり、異常な発汗や体臭の変化、肌に赤みや湿疹、ニキビが現れることがあります。特に皮膚はピッタと関連が大きいため影響を受けやすく、紫外線や高温も加わってトラブルが起こりやすくなるため、注意が必要です。
また、ピッタは「消化を司るドーシャ」であるため、胃酸の過剰分泌や腸の過活動が起こりやすくなります。胸やけや下痢、腹痛、食欲不振などの消化不良症状は、ピッタ過剰のサインといえるでしょう。
さらに精神面では、怒りっぽさ、イライラ、不眠なども典型的なピッタの乱れによる症状です。特に興奮して寝つきが悪くなる、夢を多く見る、夜中に目が覚めるといった症状は、日中に受けた刺激が処理しきれず、ピッタが心の中でも過剰になっているサインとされています。
このように、体にも心にも多面的な不調が現れるため、ピッタを穏やかに整える生活習慣と食事の実践が、夏のセルフケアとして非常に重要になります。
夏におすすめの野菜とその理由
アーユルヴェーダでは、「季節に調和した食材選び」が健康の基本とされています。特に夏はピッタが高まりやすく、体内に熱がこもりがちになるため、「冷性」「消化の軽さ」「水分の豊富さ」を備えた野菜を意識して選ぶことが大切です。
また、ピッタは火のエネルギーを持つため、食事によって「熱」「酸」「刺激」が加わるとますますバランスを崩しやすくなります。そのため、夏の野菜選びでは「ピッタを鎮める味(甘味・苦味・渋味)」を持ち、「辛味・酸味・塩味」の強すぎるものを避けることがポイントです。
こうした視点で見たときに、日本でも手に入りやすい夏野菜の中には、アーユルヴェーダの知恵と非常に相性のよいものが多くあります。これらを日々の食事に上手に取り入れることで、体内の熱をコントロールし、夏バテやイライラ、消化不良を予防・緩和することができます。
ピッタを鎮める野菜の選び方
ピッタを鎮めるための野菜を選ぶ際には、以下のような基準を参考にすると良いでしょう。
- 水分が多い:熱を排出し、潤いを与える
- 苦味・甘味・渋味を含む:ピッタの刺激をやわらげる
- 軽くて消化しやすい:アグニ(消化の火)を乱さない
- 色が淡く、刺激が少ない:白、緑、黄色系の野菜が望ましい
- 地上で育つもの:重さのある根菜よりも、果菜や葉菜が理想的
逆に、赤唐辛子、にんにく、玉ねぎ、トマトなどの辛味・酸味が強い野菜や、揚げ物と相性の良い重たい食材は、夏には控えめにすることがすすめられています。
アーユルヴェーダが推奨する具体的な夏野菜(きゅうり、ゴーヤ、なす、ズッキーニなど)
ここでは、アーユルヴェーダ的にピッタを鎮める効果が期待できる、夏にぴったりの野菜をご紹介します。
- きゅうり
 水分が約95%と非常に多く、体を内側から冷やし、熱を排出する働きがあります。利尿作用にも優れ、むくみやほてりを緩和してくれます。生食も可能ですが、体が冷えやすい方や胃腸が弱い方は、軽くスチームして温性スパイスと組み合わせるのが◎。ヨーグルトとの組み合わせ(ライタ)はピッタの鎮静に優れていますが、冷え体質の人は控えめにするのがよいでしょう。
水分が約95%と非常に多く、体を内側から冷やし、熱を排出する働きがあります。利尿作用にも優れ、むくみやほてりを緩和してくれます。生食も可能ですが、体が冷えやすい方や胃腸が弱い方は、軽くスチームして温性スパイスと組み合わせるのが◎。ヨーグルトとの組み合わせ(ライタ)はピッタの鎮静に優れていますが、冷え体質の人は控えめにするのがよいでしょう。
皮膚の熱や赤みを鎮める効果もあるので、外用でパックとしても使用可能です。
- ゴーヤ(にがうり)
苦味が強く、体内の熱を鎮め、ピッタによる過剰な胃酸や炎症を穏やかにする作用があります。肝機能を整え、夏バテの予防にも有効とされるスーパーフード的存在です。ココナッツミルクやターメリックとの相性も良く、カレーにすると苦味も和らぎます。 - なす
 独特の渋味と苦味を持ち、体内の余分な熱を冷ます効果があります。加熱することで甘味も引き出され、消化しやすくなるため、ギーやオリーブオイルと組み合わせた煮物やグリル料理に向いています。
独特の渋味と苦味を持ち、体内の余分な熱を冷ます効果があります。加熱することで甘味も引き出され、消化しやすくなるため、ギーやオリーブオイルと組み合わせた煮物やグリル料理に向いています。 - ズッキーニ
ウリ科の野菜で、水分が多く、体を冷やしながらも食べごたえがあり、食事の満足感を高めてくれます。味があっさりしているため、スパイスの風味を活かした調理がしやすく、ピッタ体質の方にも非常に適しています。 - オクラ
消化管を保護するネバネバ成分が豊富で、腸内環境を整える働きがあります。ピッタが強まると腸の働きが過敏になりがちですが、オクラはそのバランスを穏やかにしてくれる食材のひとつです。 - 冬瓜
 カリウムやビタミンCを多く含み、低カロリーで消化が良いのが特徴です。カリウムは体内の余分な塩分を排出する働きがあるため、むくみ解消や高血圧予防に効果が期待できます。甘味と少しの苦味があり、ピッタを強く鎮静してくれます。特に体内の熱、炎症傾向を和らげ、消化器を保護します。ジュースにすると強い清涼作用がありますが、冷え体質の人には注意が必要です。
カリウムやビタミンCを多く含み、低カロリーで消化が良いのが特徴です。カリウムは体内の余分な塩分を排出する働きがあるため、むくみ解消や高血圧予防に効果が期待できます。甘味と少しの苦味があり、ピッタを強く鎮静してくれます。特に体内の熱、炎症傾向を和らげ、消化器を保護します。ジュースにすると強い清涼作用がありますが、冷え体質の人には注意が必要です。
アーユルヴェーダで冬瓜はSattvic(純質)な野菜の代表格とされ、心を落ち着け、集中力や記憶力を高める食材としても扱われています。
これらの野菜を意識して取り入れることで、ピッタの性質である「熱」や「炎症」への予防的な食養生が可能になります。
生野菜はNG?加熱のすすめと注意点
夏は生野菜や冷たいサラダを食べたくなる季節ですが、アーユルヴェーダでは「冷たいもの=消化力(アグニ)を弱める」とされており、生野菜は基本的に“控えめ”にするのが推奨されています。
とくに、日本のように湿度が高く、胃腸が弱りやすい夏には、冷蔵庫から出したばかりの生野菜サラダはアグニに負担をかけやすく、ガスが溜まる、下痢っぽくなる、食欲が落ちるといった不調の原因にもなりかねません。
ではどうすればよいのかというと、「軽く火を通す」「温性のスパイスと組み合わせる」「室温に戻して食べる」といった工夫をすることで、ピッタを抑えながらも消化に優しい形で野菜を摂取することができます。
たとえば、ズッキーニやなすをスチームしてからコリアンダーやフェンネルと和える、きゅうりを軽く炒めてギーと合わせる、といった調理法がその例です。生野菜を食べたい場合でも、スパイスドレッシングを活用して消化の火を助けるとよいでしょう。
アーユルヴェーダ的 夏野菜の調理法ベスト5
アーユルヴェーダでは、「何を食べるか」だけでなく「どのように調理するか」も体調に大きな影響を与えると考えます。特に夏は、消化力(アグニ)が揺らぎやすく、冷たいものや重たいものによって不調を招きやすくなるため、調理法を工夫して“消化にやさしく、熱をこもらせない”ことが重要です。
一般的には、高温の油で炒めたり揚げたりする調理法はピッタを刺激しやすいとされるため、「蒸す」「煮る」「軽く温める」などの水分を含んだやさしい調理法が推奨されます。
また、調理時にはスパイスやギー(精製バター)などを適切に使うことで、消化の助けになり、野菜の持つ薬理効果をより高めることも可能です。以下に、アーユルヴェーダの知恵を活かした夏に最適な調理法とレシピ例を5つご紹介します。
炒めるより「蒸す・煮る」が基本
夏は体内にすでに熱がこもりやすいため、炒め物や揚げ物のような“火のエネルギーが強い調理法”は避けたいところです。代わりに、水分を加えてやさしく火を入れる「蒸す」「煮る」といった調理法が、体への負担が少なくおすすめです。
蒸すことで、野菜本来の水分と栄養素を保ちつつ、柔らかくなって消化しやすくなります。また、煮る場合には、ターメリックやコリアンダーなどのピッタを鎮めるスパイスを加えることで、抗炎症作用や消化促進効果をプラスできます。
蒸し野菜はシンプルに塩とギーをかけるだけでもおいしく、煮物は野菜をギーとスパイスで軽く炒めた後に水を加えてコトコト煮込むことで、優しい風味と深みが生まれます。
ピッタを鎮めるスパイスの使い方(コリアンダー、フェンネル、ターメリックなど)
スパイスはアーユルヴェーダにおいて「食事を薬に変える鍵」とも言われています。夏におすすめのスパイスは、以下のように体を冷ましながら消化の火を整えてくれるものが中心です。
- コリアンダーシード:清涼感のある香りで、ピッタを抑える作用があり、利尿効果や食欲増進にも有効。ホールでもパウダーでも使えます。
- フェンネルシード:甘くやさしい香りで胃腸の緊張を和らげ、消化を助けます。特に女性の体にもやさしく、夏のスープや野菜炒めに加えるのがおすすめ。
- ターメリック:抗炎症作用が高く、夏の肌トラブルや内臓の炎症を予防。クセが少ないため、ギーとともにどんな料理にも使いやすい。
これらのスパイスは単体で使うよりも、ギーで軽く熱して香りを引き出してから野菜と合わせると、薬効がより高まり、味もまとまりやすくなります。ピッタが強まる夏には、カイエンペッパーやブラックペッパーなどの辛味スパイスは控えめにしましょう。
夏にぴったり!ひんやり温かいギー蒸しレシピ
「冷たいけれど冷やしすぎない」――そんな夏向けの理想的な一品が、アーユルヴェーダ流のギー蒸し野菜です。
《レシピ例》
材料:きゅうり1本、ズッキーニ1/2本、コリアンダーシード小さじ1、ギー小さじ1、塩少々
- きゅうりとズッキーニは薄めの輪切りにし、軽く塩をふって10分ほど置き、水気を拭く。
- ギーを鍋に入れ、コリアンダーシードを加えて香りが立つまで加熱する。
- 野菜を加えて軽く絡めたら、少量の水を入れ、蓋をして3〜4分蒸し煮にする。
- 常温まで冷ましたら、仕上げにレモン汁を数滴垂らすと爽やかさが引き立ちます。
この一品は、温かさと冷たさのバランスが絶妙で、消化を妨げずに体を涼しく保ってくれる副菜になります。
サラダ感覚で楽しむ「クールキチュリ」レシピ
キチュリ(キチディ)は、アーユルヴェーダで「消化を休ませながら栄養を与える」理想的な食事とされている一皿です。豆と米をスパイスでやさしく煮込むこの料理を、夏仕様にアレンジしたのが「クールキチュリ」です。
《レシピ例》
材料:ムングダル(皮なし)1/4カップ、バスマティライス1/4カップ、水2カップ、ギー小さじ1、ターメリック少々、フェンネルシード小さじ1、コリアンダーパウダー小さじ1、塩適量
- ムングダルとライスを洗って30分浸水後、やわらかくなるまで煮る。
- ギーとスパイスを別の鍋で熱し、香りが立ったら煮た豆と米に加える。
- 常温まで冷まし、粗熱が取れたらレモン汁を加える。
- 小ねぎやカイワレをトッピングして、夏らしくサラダ感覚でいただきます。
栄養バランスがよく、消化も軽いため、食欲が落ちた日や疲れた胃腸のリセットにもぴったりです。
夏バテに効く「ゴーヤとココナッツミルクのカレー」
苦味と甘味を同時に取り入れられる、夏バテにうってつけのアーユルヴェーダ的カレーがこちら。ゴーヤはピッタの過剰な熱を鎮め、ココナッツミルクは冷却性と滋養を兼ね備えた万能食材です。
《レシピ例》
材料:ゴーヤ1/2本、玉ねぎ1/2個、トマト1個、ココナッツミルク200ml、クミン小さじ1、フェヌグリーク少々、ターメリック小さじ1/2、ギー大さじ1、塩適量
- ゴーヤは薄切りにし、塩を振って10分置いてから水気を拭き取る。
- 鍋にギーを熱し、クミンとフェヌグリークを入れて香りを出す。
- 玉ねぎ・トマト・ゴーヤを加えて軽く炒め、水を50mlほど加えて5分煮る。
- ターメリックと塩で味を整え、最後にココナッツミルクを加えてひと煮立ちで完成。
ほんのり苦味のあるゴーヤとまろやかなココナッツの組み合わせが絶妙で、食欲がなくなりがちな夏でもスルリと食べられる一品です。
体質別・夏野菜の取り入れ方アドバイス
アーユルヴェーダでは、人の体質(プラクリティ)を「ヴァータ」「ピッタ」「カパ」という3つのドーシャのバランスによって分類します。同じ夏という季節でも、人によって食べるべきもの・避けたほうがよいものが異なるのは、このドーシャの違いによるものです。
夏は全体的にピッタが増えやすい季節ですが、もともとピッタ体質の人は特に影響を受けやすく、ヴァータ体質やカパ体質の人もそれぞれの傾向に応じた食材・調理法を意識することが大切です。ここでは体質別に、夏野菜をどのように取り入れるべきかを詳しくご紹介します。
ピッタ体質の人向け:冷やしすぎ注意とギーの活用
もともと「火」のエネルギーが強く、筋肉質で集中力があり、情熱的な傾向をもつピッタ体質の人は、夏になると熱がさらに過剰になり、吹き出物、怒りっぽさ、下痢や胃の不調などが現れやすくなります。
そのため、ピッタ体質の人は「冷性のある野菜」を積極的に摂りながらも、「冷やしすぎないようにする」ことがポイントです。たとえば、きゅうりやなすをスチームしたり、ココナッツミルクと一緒に調理したりといった、やさしい温度感の調理が理想的です。
また、ピッタを鎮める万能食材であるギー(精製バター)はぜひ活用したいアイテム。ギーは内臓を潤し、過剰な熱を抑え、穏やかにエネルギーを与えてくれます。ギーでスパイスを温めてから野菜に和える「タルカ」の技法を取り入れることで、料理の薬効が一段と高まります。
ヴァータ体質の人向け:温野菜で消化をサポート
ヴァータ体質の人は「風」のエネルギーが強く、体が冷えやすく、乾燥肌気味で、神経が繊細な傾向があります。夏の暑さ自体で大きくピッタが増えることは少ないものの、冷房や冷たい飲食物によってヴァータが乱れることが多いのがこのタイプの特徴です。
この体質の方にとって重要なのは、「冷やしすぎないこと」と「消化を助けること」。冷たい生野菜やサラダは避け、スチーム野菜やスープにして体を温めつつ潤す工夫が有効です。
オクラやズッキーニ、なすなどを煮物にしたり、ムング豆と一緒にキチュリにするのもおすすめ。スパイスはフェンネルやクミン、ヒング(アサフェティダ)など軽やかで整腸作用のあるものを選ぶと、胃腸が安定しやすくなります。
カパ体質の人向け:スパイス使いで代謝アップ
カパ体質は「水」と「地」のエネルギーを多く持ち、体格がしっかりしておおらかで安定感がある反面、代謝が低く、むくみやすく、夏でもだるさや重さを感じやすい傾向があります。
カパ体質の人にとって夏は、冷たい食べ物を取りすぎると代謝がさらに低下し、体が重だるくなったり、食欲不振に陥ったりしがちです。そこで、冷却性のある野菜を取り入れつつも、ピリッとしたスパイスを効かせて代謝を刺激することが鍵になります。
ゴーヤやズッキーニ、ピーマン、枝豆などは相性がよく、炒め物やスープにして、ジンジャーやマスタードシード、少量のブラックペッパーを加えることで活力が引き出されます。また、塩分の摂りすぎに注意しつつ、レモンやライムなどの酸味を加えて味のメリハリをつけるのもおすすめです。
日々の食事で実践!アーユルヴェーダ的な夏の献立例
理論がわかっても、いざ毎日の食事となると「何をどう作ればいいかわからない」という声は少なくありません。そこでここでは、アーユルヴェーダ的な視点から考えた、夏を健やかに乗り切るための1日の献立例をご紹介します。
どれも特別な材料を使わず、日本の家庭でも手に入る食材で構成しているため、すぐに実践できる内容です。
朝食:ギーとスパイス香る「ターメリック粥」とスチーム野菜
朝はまだ消化力が目覚めきっていない時間帯。重たいパンや冷たいヨーグルトではなく、温かくて軽く、消化にやさしい粥がおすすめです。
白米またはバスマティライスを軟らかく煮て、ギーとターメリック、クミンで香りをつけた「ターメリック粥」は、体を内側から穏やかに温め、胃腸を整えてくれます。添える副菜として、きゅうりやズッキーニを軽く蒸した野菜に塩とレモン汁をふるだけのシンプルスチームも◎。
昼食:消化を助ける「夏野菜とムング豆のキチュリ」
昼は1日の中でもっとも消化力が強くなる時間帯。ここではしっかり栄養を摂ることが大切ですが、夏場はあまり重たすぎないようにするのがポイントです。
ムング豆とバスマティライス、ズッキーニ、なす、トマトなどの夏野菜を一緒に煮込んだ「夏キチュリ」は、胃腸に優しく、体をクールダウンさせながらも満足感があります。ターメリック、コリアンダー、フェンネルをベースにしたスパイスで風味をつけると、食欲も刺激されて一石二鳥です。
夕食:ピッタを鎮める「ゴーヤとココナッツの野菜スープ」
夕食は、1日の疲れを癒し、消化に負担をかけないことを重視します。おすすめは、ゴーヤとオクラ、ズッキーニなどをココナッツミルクと共に煮込んだスープです。
味つけはシンプルに、ギーと少量のターメリック・フェヌグリーク・塩を使い、刺激は抑えながらもほんのりスパイシーな温かさを残すようにすると、心身ともにリラックスできます。寝つきがよくなる効果も期待でき、夏の夜にぴったりの一品です。
ハーブティー:一日を通して「コリアンダーティー」や「ミントティー」を
食事以外では、飲み物でもピッタを整えることができます。おすすめはコリアンダーシードを煮出したコリアンダーティーや、フレッシュミントを加えたミントティー。これらは体を冷やしすぎず、内臓を穏やかにクールダウンさせてくれます。
まとめ:夏野菜と調理法でピッタを整え、夏を快適に
アーユルヴェーダの知恵は、単なる伝統医学の枠にとどまらず、現代の日本の夏にも無理なく応用できる、実用的かつやさしい健康法です。特に夏は、外気の暑さに加えて、冷房・冷たい飲食物・紫外線などの刺激が重なり、知らず知らずのうちに体と心に熱がこもりやすくなる季節。そのため、ピッタの乱れを整えることが、快適な毎日への鍵となります。
大切なのは、「体を冷やすこと=冷たいものを摂ること」ではないという点。アーユルヴェーダでは、“冷やしすぎない”冷却法を推奨しており、スチームや煮物といったやさしい加熱調理を通じて、消化にやさしく、内臓をいたわる食事を提案しています。
また、ギーやスパイスの活用によって、料理の味だけでなく、薬理的な効果も高めることができるのも魅力です。スパイスは一見ハードルが高そうに見えますが、ほんの少量のコリアンダーやフェンネルからでも始められます。
旬の野菜を、体に合った方法で調理し、季節に寄り添って食べること。それは、自分自身を大切にすることでもあります。体も心も穏やかに。アーユルヴェーダの夏野菜で、この夏をもっと軽やかに、心地よく過ごしてみませんか?
無料個別説明会で、“あなたにとっての学びの生かし方”がわかります
英国アーユルヴェーダカレッジでは、個別での無料説明会も開催されています。
「今の私に、必要な学びなのか?」「仕事や家事と両立できる?」といった不安も、やさしく丁寧に相談にのってくれます。
また、オンライン受講や週末クラスも用意されており、無理なく続けられる柔軟な学び方が選べるのも魅力です。
本気でアーユルヴェーダを学びたい方へ
総合プロコースの詳細はこちらからどうぞ
>>総合プロコース
★プロフェッショナルなアーユルヴェーダセラピストの育成
★1年間510時間の本格的なカリキュラム
★アーユルヴェーダを深く学び、もっと健康で美しくなりたい
★セラピストとして多くの人の健康と幸福に貢献したい
★サロンを開業して、自分の自由な時間で仕事をしたい
★現状のスキルと掛け合わせてカウンセリングの質を高めたい
こんな皆さまの学びを徹底サポートします。
アーユルヴェーダの独自のオイルマッサージ法タイラヴィマルダナが学べるのは 日本国内では本校のみとなります。
入学をご検討の方は、山田泉校長の無料説明会にいらしてください。
個別無料説明会の詳細はこちらからどうぞ
>>山田泉の個別無料説明会
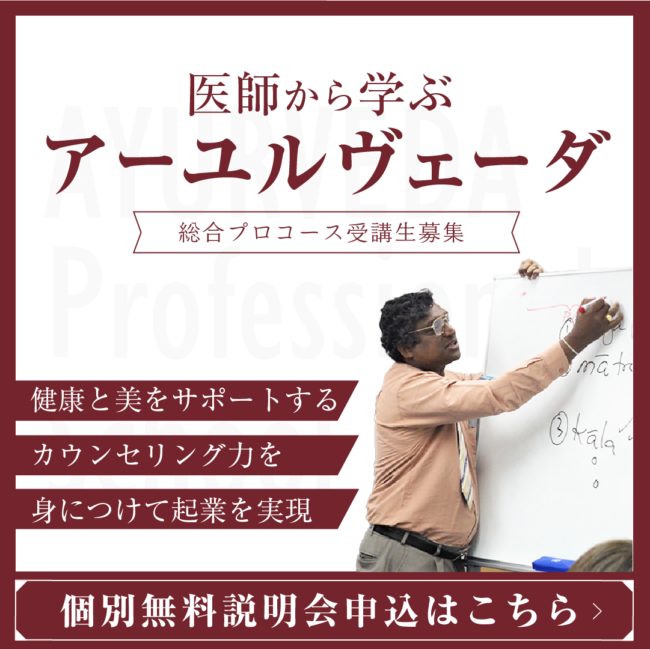
リアルな受講生の声はこちら
ライター&編集担当

東京都出身。気になることはすぐ確かめたくなる好奇心旺盛のヴァータ体質。
misaki 記事一覧へ
コロナ禍での体調管理をきっかけにアーユルヴェーダに出会う。自律神経の乱れやPMSなど、それまで悩んでいた不調にも対処できることがわかり、学びを深める。知識が増えるにつれ体調を崩すことが激減。身体が弱いと思っていたがセルフケア不足だったことに気づく。
現在は自分の体の変化を楽しみながらアーユルヴェーダを実践中。
おだやか、ていねい、マイペースな人生を送ることが目標。
英国アーユルヴェーダカレッジ56期卒業
アーユルヴェーダビューティーセラピスト/ライフカウンセラー